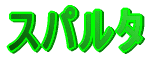
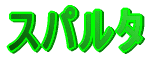

スパルタといえばレオニダス大王です。前490年にアテネの北方約150㌔の隘路で、7万とも10万とも言われるペルシャの大軍を前に、ギリシャ連合軍・最強の部隊=スパルタ軍=を率いて果敢に戦いました。
その数わずか300人。王とともに戦ったスパルタの精鋭は全滅しましたが、この戦いに手こずったペルシャ軍は、アテネへの進軍に時間をとられ、アテネ防衛軍に立て直しのチャンスを与えたともいわれます。結果としてペルシャ軍はサラミス海戦で敗れ、ギリシャ制覇の夢を果たせなかった。
スパルタの町外れ、緩やかな丘の上のグラウンド前ににレオニダス王の像があります。テルモピュライの像とほぼ同じ姿です。精悍な像は紀元前の戦いを彷彿とさます。



ギリシャの道路を走っていると、急なカーブや下り坂の崖側に、小さな箱、時には石造りで2㍍ほどの高さの四角いものが作られています。初めはいったい何だろうと、不思議に思いましたが、交通事故で亡くなった人の冥福を祈る「小教会」だと聞きました。
4つも5つも並んでいたり、古く錆びたトタン作りがあるかと思うと、立派な小型の建物みたいなものもあります。増える一方なのでギリシャ政府は新たに作ることを禁止したのですが、まだ建てる人は多いようで、無闇と撤去するわけにもいかず、困っているそうです。
80年代の終わりまで、ギリシャは「クラッシックカーの宝庫」などといわれるほどポンコツ車が走っていましたが、今世紀に入ってからは、そうした車も見られなくなりました。
遺跡の修復ははごく一部だけです。





▼寄り道
レオニダス王の像を見ながら古代の戦いを勝手に思い描いていました。強かったスパルタの戦士たちは、7歳から集団生活で徹底した教育を受けたそうです。軍事教育はその中でもっとも大切なことだったのです。前500年頃のスパルタは人口が約7万人だったといいます。そのうち支配者層の市民は2000人ほどしかいなかったのです。
強い男たち、王に絶対忠誠を誓う精悍な兵士の集団なくして、国家は成り立ちません。生まれたときに柔弱だと判断された子供は、即座に殺されたとも言われます。弱いものを引き連れていては、果敢な戦いに支障を来すからでしょう。
スパルタ教育という言葉は、ここから生まれました。スパルタンという言葉もあります。平和な世でも男が秘かに憧れるのは、やはり強さなのでしょう。もっともパソコンで投資、投機、ペテンまがいのファンドに熱中する人も増えたので、肉体の頑強さは今の世の中の“強さの基準”には入らないのかも知れません。


修道院は岩壁の途中にあります。上も下も切り立っています(右)

スパルタへはアルゴニック湾南側の入り口、たレオニディオからクルマで山越えをしました。急峻な岩山が多く、舗装はされていても狭い道は、思いの外大変でした。
峠とでも言えそうな所の断崖に、修道院がありました。下から見えたときには、あんな岩壁に張り付くように、よくも建物を造ったものだと思ったものです。
岩を上手に利用し、道をを刻み、少し緩い岩の斜面に建物がようやく建てられていました。中へ入っていくと、なにやら修道女たちの作ったものが置いてあり、お土産として売っているようでした。
スパルタの遺跡には太いオリーブの切り株(上)がありました。いかに長い年月、放置されていたのかが分かります。峠に入る前には古いオリーブ畑があり、直径3㍍は下らない古木が沢山あるのには驚きました。

しかし、そんな人の多くがスポーツを見るのが大好きですから、心の底では、自分の精悍な姿を描いているのでしょう。どこかに大昔の体を使った闘争の記憶が残っているのかも知れません。
ふとグラウンドを見ると、女性が1人、トラックを軽やかに走っていました。男の姿は見当たりません。スパルタも“普通の街”になったのでしょう。レオニダス王の像はグラウンドに背を向け,東北東のアテネ方面を見据えて立っていました。