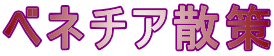ベネチアの海 翼を持つライオン ベネチア散策    海から見るベネチアの街 ドロミテの山群から流れ出る川が、アドリア海のおとなしい海に押し流してきた土砂で浅瀨を作る。"ラグーン=英、ラグーナ=イタリア)と現地で呼ぶ堆積した島、または浅瀨が形成された。そこへ6世紀頃、異民族に追われて本土から逃げ出し、砂州などに住み着いた人々の作った国がベネチアの始まで、小島の高い場所を見つけて家を建てた。人口が増えるにつれて、砂州を拡張したり、丈夫にするために頑丈な木材を深く打ち込んで基礎を固めた。その数は膨大でちょっとふざけた言い伝えまである。 「ベネチアを裏返せば、森林が生まれる」と。  頑丈な建物は砂州に打ち込まれた丸太が支える 街は小島が基礎となり、その周辺に干拓などで乾いた部分を作り出している。従って、船でなければ行き来出来ないし、その航路は難解極まる。海の干潮などによる、浅い水路で航行が困難になるため、自然の防御が外敵を防ぎ、街は次第に発展した。ドージェと呼ばれる総督(697年)を頂点とする政体が発達し、836年にイスラムの侵略を、900年には、マジャールの侵攻を撃退し、国としての基礎を築いた。   サンマルコ寺院の広場と鐘楼 6~8世紀には各国が独自の守護聖人を持っていたが、ベネチア政府は商人達の動きに注目した。彼らはエジプトで倒れた聖マルコの遺骸をベネチアへ運んで祀るためにサン・マルコ寺院を作る大事業に着手した。時の政府は、守護聖人の象徴、翼を持つライオン、をベネチアの紋章とした。  鐘楼から見る広場と寺院のドーム 以来、砂州の街は商業都市として発展を続け、海洋進出とともに軍船も整備、10世紀には、イスラムとの交易も開始した。フランク王国の支配も際どく逃れ、800年には東ローマ帝国とフランク王国間で結ばれた条約で、ベネチアは東ローマ帝国に属するが、フランク王国との交易も開始し、商業・貿易都市へと大きく前進した。かくして兵器・造船などでは世界的な交易の拠点となっていった。  その後も第4回十字軍側についたベネチア艦隊はコンスタンチノーブル(イスタンブール)の東ローマ帝国を攻め、勝利した代償としてクレタ島を得たほか、アドリア海沿岸の港湾都市はそっくりベネチアの影響下に置かれた。さらにフランク側に加わったベネチアは、東ローマ帝国の分割で莫大な利益を手にし、地中海でヨーロッパ最大の勢力を誇る国家になっていった。東地中海から黒海は”ベネチアの海”と言える状態になっていた。  しかし、ベネチアの栄華にも限界があった。オスマントルコの勢力拡大で次第に押され、さらにはナポレオンの野望の下、ヨーロッパに君臨する海洋帝国の命脈は絶たれた。しかし、長い栄光の時代に培ったノウハウや、巧妙な外交戦略を展開し紋章(右)、市旗に往時からのライオンを描き、イタリアの海洋都市として交易、観光などで繁栄を続け、今日へと続いている。 アドリア海東岸は現在殆どをがロアチアとなっているが、港々の城門などには、ライオンの彫り物が有り、ベネチア支配の名残を留めている。 |