 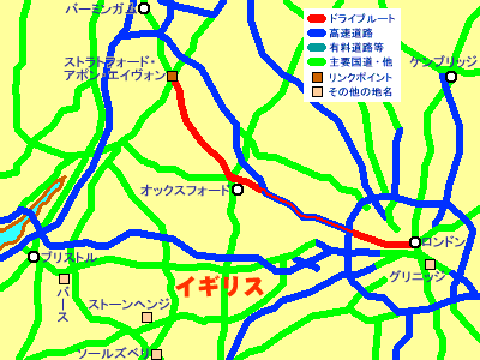 ここで紹介する地域は、クルマを運転できる人がイギリスを訪れた時に、数日の余裕が有れば気張らずに見て回れるところです。何しろヨーロッパでハンドルを握ると、右側通行なので戸惑うことが多いのです。とっさの回避操作にしても、右ハンドルと左ハンドルでは異なります。運転は意識しないでもスムーズにクルマを動かせることが安全につながります。その点、左側通行は日本と同じだし、道交法はほぼ世界共通なので、海外ドライブに慣れていない人でも、そう苦労せずに流れにK入り込めるのではないかと思います。 時間があったら、ちょっと一巡りというのも悪くはないと思います。賑わう街、丘陵の牧草地帯、古い城、先住民の遺跡、風呂の語源伴ったバースの温泉…。決行楽しめるコンパクトなコースです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 イングランドの丘陵地帯を走った。ロンドンを出発してからまるで大陸のように感じるのが、同じ島国でも、日本との大きな違い。急峻な山G海岸近くまで迫るのが日本だが、イギリスは平均的に見ると丘陵が圧倒的で、山は限られた地域にある。のんびりした気分でドライブしながらイングランドの中央部から南部方面への田舎道を辿り南ウェールズの古城や自然の風景を訪ねてみた。古代巨石文明を忍ばせるストーンヘンジは、国際的に有名。高速道路網から少しずれるが、時間の許す限り訪れることをお勧めする。
ゆるやかな起伏の中に羊が群れ、点在する小さな村には茅葺きの古い民家が残り、イギリスのカントリーを代表する風景である。
イギリスは日本と同様、右ハンドル左側通行の国だ。交通法規もほぼ同じ。ただし、距離はマイル(1マイル=1.6km)、またスピードは速く一般道路でも60マイル(約90km)以上で走り抜けていく。注意したい。 長距離コースのためイングランド地方を2回に、またウェールズ地方を1回と、計3回に分けて紹介しよう。
<コース> ロンドン(London)-オックスフォード(Oxford)-ストラトフォード・アポン・エイヴォン(Stratford Upon Avon)-コッツウォルズ(Cotswolds)丘陵を経て-バース(Bath)-ストーンヘンジ(Stonehenge)-ウィンザー(Windsor)-ロンドン 全行程 約1,000M(マイル)=約1,600km、7泊8日
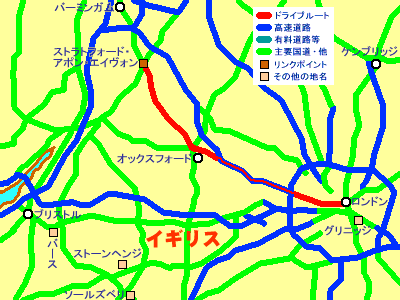 <ルート付近のリンクポイントをクリックしてみてください> 日本で一般に使われている「イギリス」という国名はイングランドを語源としているが、正式には「グレート・ブリテンと北アイルランド連合国」(The United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland)という。イングランドとウェールズとアイルランドそれに北アイルランドの連合国だが、国民それぞれ4つの国という意識が強い。 ここでは長い国名を割愛し、便宜上「イギリス」と呼ぶ。ただし、今回の旅はイングランド地方とウェールズ地方である。 ●ロンドン(London)
●オックスフォード(Oxford)へ 市内からはA40号線を辿るとそのまま高速道路M40号線に続く。ロンドンから西北西に60マイル(約100km)、テムズ河の上流沿いにある世界最古といわれる学園都市オックスフォードへ。 イギリスは日本と同じ左側通行、というより日本がイギリス式左通行を取り入れたのだ。高速道路(Mで示されたMotorway)の最高速度は道路上には明示されていないが、高速道路は70マイル(112km)。インターチェンジは地名と同時に番号で表示されているので見知らぬ地名を覚えるより、あらかじめ番号をマークしよう。 また高速道路はウェールズとの境界であるセバーン川(River Severn)に架かる一部の橋やトンネルを除くと基本的には通行料は無料。一般道路も指示がない限り同じ70マイルで、村や町の中や見通しの利かないところでは最低30マイル(48km)とある。ただし、何事にも規則には厳しい国、くれぐれも安全運転を…。
●オックスフォード(Oxford) 現在、15万人の人口の町に内1万3,000人が学生というオックスフォードは40あまりのカレッジがあり、このカレッジの総称がオックスフォード大学といい、これらのカレッジに学生が在学している。 もとは羊毛の集散地だったこの地に13世紀に修道士が集まり、次第にカレッジが形成されていった。修道士の多くは伝道士であると同時に哲学者でもあった。こうした人々が約1世紀後1,500人の学者からなるオックスフォード大学として発展していった。
グレート・トム(Great Tom)の名で知られている古い大きな鐘は、かつてカレッジの門限を知らせていたもの。いまも当時の午後9時5分に鳴らしている。 1264年に創立した最も古いカレッジの一つマートン・カレッジ(Marton College)には日本の現皇太子殿下が留学されていたことでも有名だ。 またこのカレッジの図書館の蔵書が多く充実していることでも名高い。 世界最古の図書館ボドリアン(The Bodleian Libraly)はイギリスで出版されるすべての本が収められている。 カレッジの多くと図書館は無料または有料で見学や利用することができる。 市内全体が歴史ある建物で、裏道の小さなティルームやレストランにも古いイギリスの民家などが利用されたりしていて中世の雰囲気を残している。とくに驚いたのは石畳の狭い路地の奥に1600年代のホテルがあったこと。日本風にいえば旅籠といった感じだが、現在も営業中の看板があり、数人の客が蔦の絡まる小さな庭のベンチでティータイムを楽しんでいた。
●シェークスピアの故郷 ストラトフォード・アポン・エイヴォン(Stratford Upon Avon) 文豪シェークスピアの生誕地として知られる町でイギリスの代表的な観光地である。 オックスフォードからほぼ北へ45マイル(約70km)M40号線の高速道路をインター11のバンベリー(Banbury)で出て県道の狭い田舎道を走る。緑の牧草地に羊の群をみながら15マイル(約20km)も行ったところに石造りに茅葺きの屋根の古い民家に出会った。村に入ると古い小さな教会を中心に茅葺き屋根の民家が並んでいた。 そのはずであった。このあたりより南へ下る一帯は、中世の庶民の文化遺跡がそのまま残る村々の点在する、もっともイングランドらしい田舎の風景の続く街道なのである。 このコースについては次回に回して先を急ぐ。
●シェークスピアの生家
『ヘンリー6世』、『リチャード3世』、『じゃじゃ馬ならし』など歴史劇や喜劇を多く手がけ『ハムレット』、『オセロ』、『リア王』、『マクベス』の四大悲劇を発表後、生まれ故郷に帰り6年を過ごした1616年、52歳でこの世を去った。 現在は生家の周辺は土産屋やレストランがひしめくように建ち並び、保存された生家も観光の町の中に埋もれていた。面白かったことは今もなお偉大なるシェークスピアの実家(生家)では、父親が営んでいたように売店で“皮手袋”を売っていたことだ。もちろん現代の商魂逞しい観光業界のことだが、シェークスピアはあの世でいまだに皮手袋を売っている我が家に苦笑しているかも。 ロンドンから200km弱の距離だが、昔は都から遠く離れた片田舎であっただろうということが容易に想像できるほど、町を一歩出れば隣の村までは羊しかいない丘陵地帯が続くだけだった。 |
 |
 |
 |
 |
 |
<コース>
ロンドン(London)-オックスフォード(Oxford)-ストラトフォード・アポン・エイヴォン(Stratford Upon Avon)-チッピング・カムデン(Chipping Campden)-ブロードウェイ(Broadway)-ストウ・オン・ザ・ウォルド(Stow on tha Wold)-サイレンセスター(Cirencester)-テットベリー(Tetbury)-ペゥジー(Pewsey)-マールボロ(Marlborough)-バース(Bath)-ストーンヘンジ(Stonehenge)-ウィンザー(Windsor)-ロンドン
全行程 約1,000M(マイル)=約1,600km、7泊8日
今回行程 約180M(マイル)=約288km、2泊3日
| 道路の種類: | Mは高速道路、Aは国道。Bは日本でいう県道にあたる。これらの道路標示の数字が小さいほど重要道路だ。 |
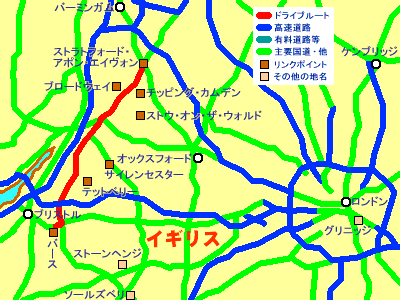
●チッピング・カムデン(Chipping Campden)
ストラトフォード・アポン・エイヴォンを出るとすぐ民家は途絶え、石や生け垣で囲った緑の羊の牧草地帯を走る。A429号線を南に8マイル(1マイルは約1.6km)を右折。ミシュランの地図には道路番号が表示されていない道を4マイルほどで、チッピング・カムデンの村に着く。
ここは13~14世紀に羊毛の町として栄えた村だ。1627年に建てられたとい村の中央にあるマーケットがいまもそのまま残る。床はすり減った石畳で長い間売り買いの人々で賑わった歴史が感じられる。
村全体が中世の様子を残し、村はずれには石造りに茅葺きの屋根の家も軒を連ねていた。
 チッピングカムデン付近の牧場 |
 この地方特有の茅葺き屋根、 石造りの家 |
また、白壁に木組みの家もあり、コンクリートやプレバブの町や村と異なり眺めているだけでも心が癒されるようだ。静かに時が流れるような村、ここに暮らす人たちも穏やかでのんびりしているようだ。
●サイレンセスター(Cirencester)へ
|
地図に県道番号も表示されないような細い田舎道をブロードウェイ(Broadway)へ。 ただ、この地方では観光客の多いブロードウェイはストラトフォード・アポン・エイヴォンから分かり易く距離も近い。この村にはアンティークやおしゃれなティールームなどがある。 |
 こんなショーウィンドウも |
 サイレンセスターの市場跡 |
ブロードウェイから県道424号線上にあるストウ・オン・ザ・ウォルド(Stow on the Wold)はこのコッツウォルズ丘陵では標高が800mと一番高い。 東西南北を結ぶ6本の道が交差する村はかつては2万頭の羊を取引したという流通の中心でもあった。 |
狭い路地にアンティークの店やみやげ物店、昔の旅籠屋を改造したような古いホテルもある。蔦のからまる老舗のホテルと清流に鱒の泳ぐバイブリー(Bibury)など数マイルおきに古く美しい村々を通り過ぎていく。その街道沿いはなだらかな緑の斜面に白い羊が遊び、晩秋の樹木は葉を落としはじめていた。
 雨のイングランド丘陵地帯 |
 サイレンセスターの北、 ヤンウォース村 |
|
サイレンセスターは村というより大きな町だ。まだイギリスがローマの植民地であった昔、ロンドンに次ぐ第二の都市だったところ。 この町に近くにはローマ時代の遺跡がある。車が一台やっと通れるような狭い道を6マイルほど行った先、行き止まりに事務所やチケット売り場の建物がある。 |
 ローマ人の遺跡を示す 小さな道標があった |
 サイレンセスター北方のローマ人の 遺跡。すっかり整備されている |
 遺跡の中のわき水。 昔からのものと聞いた |
●テットベリー(Tetbury)
 市場の跡がそのまま保存されている |
村の中心部には1665年に造られたというマーケット・ハウスがある。1700年代に改修されているが約350年前に建てられたものだ。 正面の時計台は1887年に造られたものだと、マーケットの中の案内板に書かれていた。 |
マーケットから商店街を挟んだところにはパリッシュ教会があった。紀元は680年ごろといわれているが中世の建築である塔と尖塔以外は18世紀にすべて取り壊し、ゴシック様式に立て替えられたものだとか。敷地内には無数の墓石がひしめくように立つ古めかしい教会も周囲の家並みの中に溶け込んでいた。
 中世の町並みが残る |
 舗装と駐車した車がなかったら 中世の街だ |
○寄り道
テットベリーからバースへは約25マイルとすぐ近くだ。だが、街角のみやげもの店で白壁に木組みの美しい家並の絵はがきを見つけてしまった。店の人に尋ねるとコッツウォルズ丘陵から少し南へ向かったペゥジー(Pewsey)の村だという。筆者はただちにハンドルを向けた。
 マールボロの町と記念館 |
教えられた通り入り組んだ県道を30マイルほど走ると、マールボロ(Marlborough)の町に着いた。 東西に延びる町は真ん中に駐車場のあるとてつもなく広い道路を挟んで商店街があるところだ。 |
|
イギリスの晩秋の日は短い。午後4時、雨模様の空はもう暗い。この町でホテルを見つけて泊まることにした。 町はずれの教会の塔が暮れゆく空にシルエットのように浮かんでいた。 |
 マールボロの町と教会 |
●ペゥジー(Pewsey)
ソールスベリー(Salisbuny)からA345線をエイヴォン(Avon)川沿いに北へ20マイルほど、マールボロに近い小さな町で、街道に沿って絵はがきで見つけた木組みの家や茅葺きの家が点在していた。
 ペウジーの古い民家 |
 木組み、白い漆喰。 古い民家は少なくなっている |
●バース(Bath)
 バースには古い大きなアパートが並ぶ |
風呂の語源となったバースはイギリス随一の温泉場で2000年前の古代人によって温泉保養所が開かれたのがはじまり. . 、いまなお45度の湯が1日約125万リットルも湧く。 イギリスがまだローマの支配下にあったころ、ローマ人は蒸気風呂やプールまである大浴場を築きリゾート地として栄えた。 |
|
ローマ人が去った後、浴場は荒れ果てたが18世紀にはイギリスでも指折りの行楽地となり、王侯貴族も訪れるようになった。 19世紀にはローマ浴場が発見、発掘された。ローマ浴場の地階には発掘されたギリシャのアテナ神殿跡やモザイク、コイン、儀式に使われた器などその他の資料が展示されている。 |
 野天風呂からは 教会の塔が見える |
 ローマ風呂には何種類もの 浴槽がある |
現在の建物は1617年のもの。元のアビー・チャーチ(修道院付属教会)というのは名だけでいまはバース教会としての機能だけを果たしている。

バースの町の中を流れるエイヴォン川に架かるバルトニー橋から三つの優美なアーチで支えられた橋の上にはみやげもの屋の店が並ぶ。
ウェールズの旅を終えバースで遊びロンドンへと戻る途中には有名なストーンヘンジがあり、豊かな穀倉地帯や羊の牧場などのどかな風景が続く。
また、ロンドン空港近くにはエリザベス女王が週末を過ごされたウィンザー城がそびえ建つ。そしてテムズ川沿いにはイギリスでは2番目に古いパブリック スクールの名門イートン校がある。
ウェールズの首都カーディフからロンドン空港までは距離にして約250km、高速道路M4を走れば3時間ほどだが、こうして寄り道をしながらのドライブは丸1日がかりだ。
このイギリスを代表するような観光地や風景、建築物を写真で紹介したいと思う。
 |
 |
 |
 |
 |
<コース>
バース(Bath)-A36-ストーンヘンジ(Stonehenge)-M4(高速道路)-ウインザー城(Windsor Castle)とイートン校(Eton College)
約250km、1日
| 道路の種類: | Mは高速道路、Aは国道。Bは日本でいう県道にあたる。これらの道路標示の数字が小さいほど重要道路だ。 |
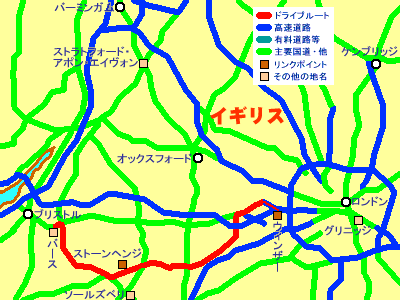
●ストーンヘンジ(Stonehenge)
ソールズベリー(Salisbury)から北へ約15km、A303号線沿いには標識がある。あたりの平原は昔から穀倉地帯といわれている。その広い農地の真ん中に直径30mの円に高さ4mあまりの大きな石柱が並ぶ。
| 紀元前3000年ころから1100年ころにかけて約5段階の行程を経て造られたという。石柱は30個、現在は石柱が17個だけ。その上に横置きの石でつないであったが、3個だけが残る。また内側にもリンクがあり、元は60個の少し小さめの石が60個もあったが、これも現在は21個だ。 |
 こんな想像図も描かれていた |
宗教儀式に使われたものらしいとか、夏至には中央の石と石の間から太陽が昇り、祭壇を照らしたことからこれを天体観測のために造られたという説が今は有力だが、約30km離れたマルボーロの丘からこの巨岩を運んで並べた本当のところは今も謎とか。
以前はこの石柱の中まで入り、手で触れることもできたが、心ない観光客の落書きや記念にと石を砕いて持ち去る者もいたため、現在はロープが張られかなり遠巻きに観ることになった。
●ウィンザー城(Windsor Castle)
ロンドン ヒースロー空港へ約10km、テムズ川の流れを見下ろす丘の上に威風堂々とそびえ立つ。現在使われている王室の居城としては、世界最大の規模を誇る。実に900年以上もの間、王室の居城として使われ続ける城は威厳に満ち、歴代王たちの権力と栄光の日々を刻んできた。現在も週末や休日にはエリザベス女王はここで過ごされる。城の中心にあるラウンド・タワーに国旗が掲げられているときは女王が滞在されているサインなのだ。ちょうどこの日は週末、天高く国旗がはためいていた。
 エリザベス女王像とウィンザー城 |
 ウィンザー城の衛兵 |
城内の一部は解放され、城門の石畳を踏みしめながら見学ルートに従って、内部を観ることができる。一番のみどころはステート・アパートメンツだ。今でも王室の公式行事や国王クラスの国賓のために使われいるいくつもの広間(92年の火災によって紛失した広間なども完全に修復されている)を一般公開しているのは、開かれた王室のさすがイギリスである。
ビクトリア女王のために造られた大階段を上がると、おびただしい数の銃や剣や鎧などの武具の並ぶ部屋だ。また歴代王の居間や主寝室とかつての七つの海を制したイングランドの栄華を、しっかりみせてくれる。
 ウィンザーを流れるテムズ川 |
 ウィンザー駅 |
|
ウィンザー城の城下町は、ロイヤルタウンとも呼ばれている。その伝統と誇りにに満ちた町の誇りは古い石畳の通りに、石造りや白壁と木組みの商店、パブ、レストランとかたくなまでに歴史の重みを感じさせる町だが、ここにもアメリカ資本のファーストフードの極彩色の看板や店があり、どこも観光客でいっぱいだった。 |
 食堂は時代がかっていた。 郵便ポストは健在 |
●イートン校
豊かな水をたたえて流れるテムズ川には鴨や白鳥が優雅に浮かぶ。歩行者のみの橋から振り返るとウィンザー城を仰ぎ観る。その城壁の下には白壁に茅葺きの古い家(レストランになっている)が見える。絵になる光景だ。対岸に渡ると、イートン校まで古い商店街が続く。
イートン校はパブリックの名門中の名門校で、日本でいう中学高校の一貫教育の学校である。世界的な名門ケンブリッジ、やオックスフォードへの登竜門であり、かつては良家の子息が通うところ。制服はいまも“えんび服”、そう、ノーベル賞受賞の田中氏が着用したあのえんび服だ。学校の行事にはシルクハットもという。
 イートン校の正門から |
 イートン校の少年 |


















