スペインの田舎道
![]()
アンドラ公国 (アンドラ公爵領国)はフランスとスペインの国境にまたがるピレネー山脈の真ん中にある人口約5万人というミニ国家。国民への課税はなく、関税もない国。世界中の品物が免税で買えるというこの国は、ヨーロッパ各地からの買い物客が年間1,000万人も訪れるという。また、ピレネーの雄大な自然をも楽しめる。
ピレネー山脈を越えると広大なイベリア半島のほとんどを占める日本の約1.3倍もの面積を持つスペインだ。
ヨーロッパの先端、そして地中海の海を隔ててアフリカ大陸と近く、古くからさまざまな人種や文化を迎え入れてきた歴史を持つ国。紀元前11世紀ごろからイベロ族、フェニキア人、ギリシャ人、ケルト族などが次々に侵入、その後カルタゴ、ローマ帝国に支配されてきた。いまでもこのイベリア半島のあちこちにはローマ時代以降の遺跡を沢山見ることができる。
|
|
|
|
スペインといえば太陽の輝く地中海沿岸の明るい風景を思い浮かべるが、内陸の大陸性気候の乾いた土地や緑豊かな北部と、異なる気候や人々の生活も変化に富んでいる。
ここでは大都市をはずして、スペインのこうした田舎をドライブしながら、歴史や自然人々の生活を紹介したいと思う。
![]()
スペインの田舎道
トゥールーズ(Toulouse、フランス)よりN20(国道)−アンドラ(Andprra)[ピレネー山脈越え]−バルセロナ(Barcelona)−アウトピスタA7(Autopista高速道路)−バレンシア(Valencia)−N322(国道)−コルドバ(Cordoba)
3泊4日 約1,050km
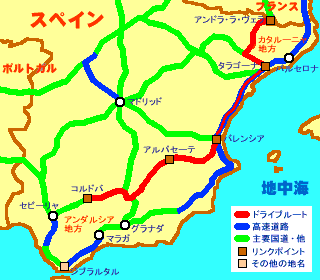
●アンドラ国境へ
サッカーW杯の日本対アルゼンチン戦で沸いたフランス・トゥールーズを出てN20(国道)をアンドラ国境を目指して南へと走る。約70kmでいままで平坦だった麦やぶどう畑の先に、まるで黒い雲が湧き出たように巨大なやまなみが見えてくる。この山の麓には、有史前の洞窟画が描かれたニォー(Niaux)の鍾乳洞がある。深い洞窟の奥には牛や鹿などの動物が顔料で力強く描かれ、スペインのアルタミラと並んで、貴重なもの。このあたりから道は狭くなり、標高を上げていく。この山道にはガソリンスタンドがない。だが、フランス側から上る車は、国境までは皆我慢だ。アンドラは免税国、ガソリン代はフランスの約半値なのだ。
 トゥールーズからアンドラ国境まで約130km。山麓から約50km。安いガソリンやワイン、たばこの日用品から日本の電気製品をはじめ世界中の安いブランド品を求めて、休日やバカンスシーズンはフランスやスペインからやってくる車でアンドラを貫く一本の道は大渋滞となる。鉄道はないので交通はマイカーとバスだけ。無税のl国なので、まとめ買いが多く、規定量以上はスペイン、フランスjそれぞれのl国の税金がかかる。
トゥールーズからアンドラ国境まで約130km。山麓から約50km。安いガソリンやワイン、たばこの日用品から日本の電気製品をはじめ世界中の安いブランド品を求めて、休日やバカンスシーズンはフランスやスペインからやってくる車でアンドラを貫く一本の道は大渋滞となる。鉄道はないので交通はマイカーとバスだけ。無税のl国なので、まとめ買いが多く、規定量以上はスペイン、フランスjそれぞれのl国の税金がかかる。
●ピレネー山中ドライブ
 アンドラに入ると高山植物の可憐な花々が咲き乱れる標高2,000mをこえる山がつらなり、スキー場のリフトがいくつも見えた。さっきまで濃い霧に視界をさえぎられていたが、国境のゲートをくぐると、吹き上げる風とともに霧が流れ、雄大なカールを描いて3,000m級の山々が姿を現した。
アンドラに入ると高山植物の可憐な花々が咲き乱れる標高2,000mをこえる山がつらなり、スキー場のリフトがいくつも見えた。さっきまで濃い霧に視界をさえぎられていたが、国境のゲートをくぐると、吹き上げる風とともに霧が流れ、雄大なカールを描いて3,000m級の山々が姿を現した。
まだ残雪を残す岩山とその美しいカールは日本アルプスの穂高を思わせるが、規模ははるかに大きい。道はこのカールの谷底を目掛けて急なカーブを描きながら下っていく。眺めのよいところには何ヶ所か駐車スペースがある。時間があれば近くをハイキングするのもよい。
●首都アンドラ・ラ・ヴェラ(Andorra la vella)
 フランス国境からN145(国道)約40km、ピレネー山脈の深い谷あいに石造りの家々が軒をならべるという、一国の首都のイメージとはかけ離れたこじんまりとした風景は、まるで箱庭のようだ。人口5万人の多くはこの周辺に住む。
フランス国境からN145(国道)約40km、ピレネー山脈の深い谷あいに石造りの家々が軒をならべるという、一国の首都のイメージとはかけ離れたこじんまりとした風景は、まるで箱庭のようだ。人口5万人の多くはこの周辺に住む。
国民は信仰深いカトリック教徒で、町には古く素朴なロマネスクの教会もある。近郊各国からの避暑地、観光地として訪れる人も多く、また、免税目当ての買い物客も多い。首都に通じる谷あいの村はこうした観光客のためのリゾートホテル建築が盛んに行われていた。市内のホテルはバス・トイレ付きツインルームで12,000ペセタ(約1万円)と安いが、シーズン中は予約なしでは無理。
スペイン
●カタルーニャ(Catalunya)地方
アンドラからスペインへの入国へは税関検査がある。検査といっても全部の車を止めて車内を調べるわけではない。抜打ち検査のようだ。アンドラから無税で大量に酒やたばこを買い込んでいないか。もし大量ならば、税金がかかる、ということだ。国境が取り払われつつあるヨーロッパで、車のトランクを開けさせられるのは珍しいことだがうなずける。
 アンドラの西南、地中海に向かって広がる地域一帯はカタルーニャ地方と呼ばれ、1977年中央政権に反発、地方分離運動の末自治権を獲得し、独自の言語(カタルーニャ語)を持つ文化圏である。その中心はバルセロナ(Barcelona)でこの街が生んだ巨匠画家、ミロ、ピカソ、ダリそしてユニークな建築家 ガウディ はカタルーニャの誇りである。
アンドラの西南、地中海に向かって広がる地域一帯はカタルーニャ地方と呼ばれ、1977年中央政権に反発、地方分離運動の末自治権を獲得し、独自の言語(カタルーニャ語)を持つ文化圏である。その中心はバルセロナ(Barcelona)でこの街が生んだ巨匠画家、ミロ、ピカソ、ダリそしてユニークな建築家 ガウディ はカタルーニャの誇りである。
アンドラからバルセロナへ下る道のこの地方のみどころはN260からN152(国道)を辿るとリポール(Ripoll)の町に着く。この町には12世紀建築の回廊の残るサンタマリア修道院がある。そこからC25(県道)を西へ約80kmほどでモンセラ(Montserrat)へ。奇怪な岩の割れ目にへばりつくように建つモンセラ修道院は「黒いマリア像」で有名。このマリア像を目指して12世紀頃からヨーロッパ各地からの巡礼が、いまも続いている。
 ピレネー山脈を一気に下るとスペインの乾いた広大な大地が広がり、わずかな高台には教会の尖塔を中心に赤茶色の屋根を持つ集落がある。その規模は大小さまざまだが、狭い路地に肩を寄せ合って、外敵から町や村を守った歴史が感じられる。
ピレネー山脈を一気に下るとスペインの乾いた広大な大地が広がり、わずかな高台には教会の尖塔を中心に赤茶色の屋根を持つ集落がある。その規模は大小さまざまだが、狭い路地に肩を寄せ合って、外敵から町や村を守った歴史が感じられる。
こうした地方の町や村を結ぶ街道沿いにはドライブインはもちろんのことレストランや宿も少ない。レストランなどの施設のある町にはナイフとフォークやベッドなどの絵で表された標識(写真)があるが、たいていは街道から離れた町村にある。田舎道の長距離ドライブは、飲み物は絶対に持参すること。食事はレストランでは2時間ほどかかるので、時間のない人は簡単な食べ物も用意すること。
●タラゴーナ(Tarragona)
 バルセロナより約100km西、地中海に面した町タラゴーナは紀元前3世紀ころから、ローマ植民地として、イベリア半島の勢力の拠点として栄えてきた。現在は黄金海岸コスタ・ドラダの中心地として別荘やリゾートホテルが並ぶ。とくに「地中海のバルコニー」と呼ばれる海に突き出た見晴らしの良い散歩道は、シーズン中は、ヨーロッパ各地からのリゾート客で賑わう。
バルセロナより約100km西、地中海に面した町タラゴーナは紀元前3世紀ころから、ローマ植民地として、イベリア半島の勢力の拠点として栄えてきた。現在は黄金海岸コスタ・ドラダの中心地として別荘やリゾートホテルが並ぶ。とくに「地中海のバルコニー」と呼ばれる海に突き出た見晴らしの良い散歩道は、シーズン中は、ヨーロッパ各地からのリゾート客で賑わう。
町の中には古代ローマ遺跡が数多く残る。みどころはロマネスク様式とゴシック様式の混交の風格ある大寺院。海岸沿いにあるローマ競技場。一見の価値のあるものはローマ時代の水道橋だ。ここは市内から6kmの山の中にある。
●バレンシア(Valenci)経由コルドバ(Cordoba)へ
 あいにくの曇り空の下、高速道路アウトピスタA7を一気にバレンシアへ約250km飛ばした。そしてバレンシアの町を迂回して内陸へ入ると、黒い雲のすぐ向こうに青い空が広がり、その先のずっと遠くまで空は青い。バレンシア地方はオレンジの産地。どんどん明るさを増す空のもとに、どこまでも続くオレンジ畑の中を走る。
あいにくの曇り空の下、高速道路アウトピスタA7を一気にバレンシアへ約250km飛ばした。そしてバレンシアの町を迂回して内陸へ入ると、黒い雲のすぐ向こうに青い空が広がり、その先のずっと遠くまで空は青い。バレンシア地方はオレンジの産地。どんどん明るさを増す空のもとに、どこまでも続くオレンジ畑の中を走る。
バレンシア市を真西へ約50km。首都マドリ−ド(Madrid)方面への道と分かれて、N322(国道)をコルドバへと向かう。ここからコルドバまで約470kmだ。だが一般道路とはいえ最高制限速度は100km。急ぐ旅ならば一日のコースだが、スペインの田舎風景を満喫しながら途中一泊したい。
 N322街道はバレンシアからセルバンテスの名作「ドン・キホーテ」の舞台カスティーリャ・ラ・マンチャ地方、そしてフラメンコと闘牛の本場アンダルシア地方を走り抜けていく道だ。
N322街道はバレンシアからセルバンテスの名作「ドン・キホーテ」の舞台カスティーリャ・ラ・マンチャ地方、そしてフラメンコと闘牛の本場アンダルシア地方を走り抜けていく道だ。
マドリードへの道と分かれて間もなくラ・マンチャ地方に入る。ラ・マンチャとはアラビア語で「乾いた大地」という意味。その名の通り、緑豊かなバレンシアの風景とは異なり乾いた褐色の大地にオリーブ畑ががどこまでも続く荒涼とした世界が広がる。
ドン・キホーテゆかりの風車の町カンポ・デ・クリプターナ(Canpo de criptana)へは分岐点から約100km、最初の大きな町アルバセーテ(Albacete)からN301(国道)をマドリード方面へ約100kmだ。
|
|
|
●食べる
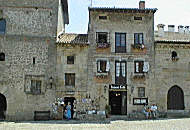 アルバセーテの町の手前30km、小さな村と村の間のわずかなぶどう畑の中に一軒の古い木造の家があった。もうとっくに昼を過ぎているのに、昼食をとるレストランも一軒のパン屋も見つけられなかった街道で、そこに書かれた「レストラン」の小さな文字も見逃さなかった。
アルバセーテの町の手前30km、小さな村と村の間のわずかなぶどう畑の中に一軒の古い木造の家があった。もうとっくに昼を過ぎているのに、昼食をとるレストランも一軒のパン屋も見つけられなかった街道で、そこに書かれた「レストラン」の小さな文字も見逃さなかった。
間口は狭かったが、ドアの中は広く、幾組かの家族連れが賑やかにテーブルを囲んでいた。すでに午後2時を回っていたが、スペインのランチタイムは午後1時から5時まで。夕食は8時から。
厚い一枚板の黒光りするカウンターや使いこんだ古いテーブルや椅子。蝶ネクタイのボーイに着飾った客。近隣からの客で多くは家族や友人たちのセレモニーが行われるのだという。村人たちの楽しみ場である。炭火焼きのヒレステーキとハウスワインのハーフボトルで、ひとり2,300ペセタ(約2,000円)。肉は柔らかく味もよかった。
 スペインのレストランはフォークの数で格付けされている。1本から5本まで。5本が最高級で料理の味ばかりでなく、店のサービスや雰囲気も判断基準となる。ただし、最高級といってもフランスほどに格式は重んじないところが、気さくなスペイン風だ。料理のメニューは多様で歴史的、地理的環境、気候人々の気質までが違うように、素材も味付けもことなる。郷土色の強いのが
スペイン料理 だ。ヨーロッパといえば肉食が多いと思われているが、古代イタリア、スペイン、ギリシャ人は魚介類や野菜が主な食べ物で、肉食はドイツ以北、北欧の人たちが食べていたもの。フォークの数でのレストラン選びは、財布との相談だが、安くても美味しい。昼食は1000ペセタ(約900円)ぐらいが手ごろ。
スペインのレストランはフォークの数で格付けされている。1本から5本まで。5本が最高級で料理の味ばかりでなく、店のサービスや雰囲気も判断基準となる。ただし、最高級といってもフランスほどに格式は重んじないところが、気さくなスペイン風だ。料理のメニューは多様で歴史的、地理的環境、気候人々の気質までが違うように、素材も味付けもことなる。郷土色の強いのが
スペイン料理 だ。ヨーロッパといえば肉食が多いと思われているが、古代イタリア、スペイン、ギリシャ人は魚介類や野菜が主な食べ物で、肉食はドイツ以北、北欧の人たちが食べていたもの。フォークの数でのレストラン選びは、財布との相談だが、安くても美味しい。昼食は1000ペセタ(約900円)ぐらいが手ごろ。
●泊まる
 田舎道での宿探しもなかなか難しい。長距離ドライバーや商人向けの宿はいくつかあったが、バス・トイレ付きのホテルとなると少ない。バレンシアとコルドバのほぼ中間、N322沿いのプエンテ・ジェナーバ(PuenteGeneve)という小さな村で
ホテル を見つけた。2階建て10室ほどの宿は1階がレストランとバー(Bar)。観音開きの窓を開けるとオリーブ畑が広がり、窓の下には一頭のロバがつながれていた。実にのどかな光景である。バス・トイレ付きツイン一泊8,000ペセタ(約7,000円)。食事は別料金でラムステーキとサラダ、ハウスワイン付きでひとり2,800ペセタ(約2,300円)。
田舎道での宿探しもなかなか難しい。長距離ドライバーや商人向けの宿はいくつかあったが、バス・トイレ付きのホテルとなると少ない。バレンシアとコルドバのほぼ中間、N322沿いのプエンテ・ジェナーバ(PuenteGeneve)という小さな村で
ホテル を見つけた。2階建て10室ほどの宿は1階がレストランとバー(Bar)。観音開きの窓を開けるとオリーブ畑が広がり、窓の下には一頭のロバがつながれていた。実にのどかな光景である。バス・トイレ付きツイン一泊8,000ペセタ(約7,000円)。食事は別料金でラムステーキとサラダ、ハウスワイン付きでひとり2,800ペセタ(約2,300円)。
 宿泊施設はそれぞれの設備などによって、ホテル(Hotel)、オスタル(Hostal)、ペンシオン(Pension)、フォンダ(Fonda)と分けられ、いずれも星の数で格付けされている。最高は星が5つだが、バスタブ付きは星3つ以上。一般にスペインのホテルは安い。ただし都市はあまりあてはまらないが、それでも星3つ以下ならば、高くても1万5,000ペセタ(約1万3,000円)位だ。すべてツインの料金でひとりはこの8割ぐらいと高い。
宿泊施設はそれぞれの設備などによって、ホテル(Hotel)、オスタル(Hostal)、ペンシオン(Pension)、フォンダ(Fonda)と分けられ、いずれも星の数で格付けされている。最高は星が5つだが、バスタブ付きは星3つ以上。一般にスペインのホテルは安い。ただし都市はあまりあてはまらないが、それでも星3つ以下ならば、高くても1万5,000ペセタ(約1万3,000円)位だ。すべてツインの料金でひとりはこの8割ぐらいと高い。
 一度は泊まってみたいのがパラドール・ナシオナル(Parador Nacional)。国営のホテルで全国84ヶ所ある。国営といってもかつての古城や館、修道院などを改造したもの。ほとんどは星が3つか4つ観光地やリゾート地にもあるが、歴史的建物を利用したものの多くは町から離れた昔の街道沿いや山の中にある。車の旅だからこそ、気軽に贅沢に楽しめる。シーズン中は早めの予約が必要だが、6月ごろまでと、10月以降は当日でもだいたい部屋はとれた。パラドールめぐりというスペイン旅行をする人がいるぐらいだから、やっぱり一度は泊まってみたい。
一度は泊まってみたいのがパラドール・ナシオナル(Parador Nacional)。国営のホテルで全国84ヶ所ある。国営といってもかつての古城や館、修道院などを改造したもの。ほとんどは星が3つか4つ観光地やリゾート地にもあるが、歴史的建物を利用したものの多くは町から離れた昔の街道沿いや山の中にある。車の旅だからこそ、気軽に贅沢に楽しめる。シーズン中は早めの予約が必要だが、6月ごろまでと、10月以降は当日でもだいたい部屋はとれた。パラドールめぐりというスペイン旅行をする人がいるぐらいだから、やっぱり一度は泊まってみたい。
●スペインのヒマワリ畑
 コルドバへあと150kmというあたりから、黄色い大地が現れた。と思う間に、いまが盛りとばかり咲き誇るヒマワリの花畑がどこまでも広がっていた。コバルトブルーの大空と黄色い大地、この見事な色彩のコントラストは、まさに情熱的だ。いくぶん起伏はあるが、真っ直ぐに延びた往復2車線の田舎道の両側に続くヒマワリ畑。その遠くには教会の尖塔があったり、この地方独特の白い家が黄色いヒマワリの中の浮かぶ。また、まだ実のつかないトウモロコシの青々とした畑が彩りをそえる。車を走らせては止め、止めて眺めてはまた走らせながらコルドバの町へと入って行った。
コルドバへあと150kmというあたりから、黄色い大地が現れた。と思う間に、いまが盛りとばかり咲き誇るヒマワリの花畑がどこまでも広がっていた。コバルトブルーの大空と黄色い大地、この見事な色彩のコントラストは、まさに情熱的だ。いくぶん起伏はあるが、真っ直ぐに延びた往復2車線の田舎道の両側に続くヒマワリ畑。その遠くには教会の尖塔があったり、この地方独特の白い家が黄色いヒマワリの中の浮かぶ。また、まだ実のつかないトウモロコシの青々とした畑が彩りをそえる。車を走らせては止め、止めて眺めてはまた走らせながらコルドバの町へと入って行った。
●コルドバ(Cordoba)
 かつてコルドバは北アフリカを含むイスラム世界の中心であった。東のイスラム教国の中心地バグダッドに対し、西のイスラム教主カリフの宮廷所在地として、10〜13世紀に栄えた。当時は300を超えるモスクがあったといわれているが、8世紀に着工され、その後も後継者にとって増築されてきたモスクメスキータ(Mezguita)がその面影をいまに伝える。堂内には大理石、縞メノウ、花崗岩で造られた円形のアーチが850本で線条細工のアラベクス模様は実に美しいものだ。また、アラビア様式のアーチにキリスト教の礼拝堂もある。
かつてコルドバは北アフリカを含むイスラム世界の中心であった。東のイスラム教国の中心地バグダッドに対し、西のイスラム教主カリフの宮廷所在地として、10〜13世紀に栄えた。当時は300を超えるモスクがあったといわれているが、8世紀に着工され、その後も後継者にとって増築されてきたモスクメスキータ(Mezguita)がその面影をいまに伝える。堂内には大理石、縞メノウ、花崗岩で造られた円形のアーチが850本で線条細工のアラベクス模様は実に美しいものだ。また、アラビア様式のアーチにキリスト教の礼拝堂もある。
コルドバにはこのほか、グアダルキビール川にかかるローマ橋や14世紀の宮殿やアラブ様式の庭園、それに旧ユダヤ人街などみどころがいっぱいだ。
夏のコルドバはアンダルシアのフライパンといわれるほど暑いので、暑さ対策を忘れずに。
|
|
|






