リスボンの町とその周辺 (1)
![]()
 ポルトガルと日本の交流は15世紀の鉄砲の伝来にはじまった。その鉄砲をいち早く取り入れた織田信長が天下をめざし、宣教師フランシスコ・ザビエルが到来、キリスト教を持ち込んだ。日本が海外をはじめて見る窓でもあった国、素朴でなんとなく郷愁を感じさせてくれるポルトガルを最初に訪れたのは、1970年代だった。
ポルトガルと日本の交流は15世紀の鉄砲の伝来にはじまった。その鉄砲をいち早く取り入れた織田信長が天下をめざし、宣教師フランシスコ・ザビエルが到来、キリスト教を持ち込んだ。日本が海外をはじめて見る窓でもあった国、素朴でなんとなく郷愁を感じさせてくれるポルトガルを最初に訪れたのは、1970年代だった。
それから何回か訪ねたがリスボン市内やシントラなどの観光地をゆっくり見物することもあまりなく、ポルトガル国内を車で走り回っていた。そこで今回(2005年12月〜2006年1月)はリスボンを中心とした一般観光地へのドライブ、および街角の風景を3回にわたり主に写真で紹介したいと思う。
ポルトガルという国などについては、1998年のドライブガイド「ポルトガル・海岸地方を走る」を参照していただきたい。
|
|
|
|
|
|
|
![]()
<コース>
リスボン(Lisboa)旧市街−ベレン(Belem)地区−エストリル(Estoril)−カルカイス(Cascais)−ロカ岬(Cabo da Roca)−シントラ(Sintra)−クリスト・レイ(Cristo Rei)
全行程 約100km
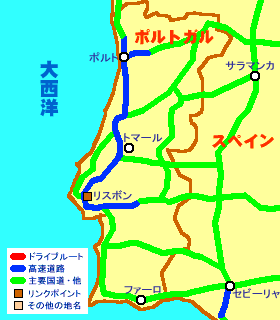
<ルート付近のリンクポイントをクリックしてみてください>
|
ポルトガルの首都リスボンを流れるテージョ(Tejo)川は、遙か遠くスペイン山中から流れ下り大西洋へと注ぐ。紀元前のフェニキア人、ローマ、やがて時代が下ってイスラム、そして大航海時代と、いつの時代にも航行する船を迎え、送り出してきた。 |
|
|
|
リスボンは大きく分けて4つのエリアがある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
狭い石畳の道を路面電車はきしみ音をたてて急坂を上っていく。その途中にあるロマネスク様式の2つの塔と壁の教会は、12世紀、ポルトガル初代王アフォンソ・エンリケスが、イスラム勢力からリスボンを奪回した後に建てたもの。フランスの名匠ロベールとベルナルドの設計といわれている。 |
|
リスボン市内を見下ろす高台にあるこの城は、数々の民族に支配されたポルトガルの歴史を物語る。ユリウス・カエサルの時代ローマ人要塞として建設されてから、5世紀には西ゴート族、9世紀にはイスラム、12世紀にはキリスト教徒、そして14〜16世紀にはポルトガル王家へと城主を代えてきた。 |
|
17世紀に着工し、1966年にやっと完成したバロック様式のリスボン一大きな教会。 |
|
|
|
ルネッサンス式の2つの鐘楼を持つ教会で、1147年にアフォソン・エンリケスによりイスラム教徒からリスボン奪回を記念して建てられた。現在の建物は1582〜1627年にかけて建造されたもの。 |
|
|
1522年、大航海時代のポルトガルの富と権力の象徴ともいえる建物。インド第2総督の息子が建てたもの。 |
|
アズレージョとは装飾タイルのことで、ポルトガル美術の代表ともいえるものである。 |
|
|
|
美術館にはこうしたアズレージョの歴史的、芸術的にも価値のあるものが展示されている。なかでも必見は、大震災前のリスボンの街を描いた大アズレージョだ。 |
|
「高い土地」を意味するこの地区は、その名の通り高台にある。とはいえ海岸通りから中心部へ向かって階段や狭い坂道にびっしりと古いアパートが建ち並ぶ。 |
|
そんな胸突き八丁のような急斜面に住む人々の生活を垣間見ながら歩いて上るのも興味深いが、ケーブルカーを利用するのもよい。 |
|
ポルトガル独特の丸いギター、キターラといわれる楽器と通常のギターの演奏にあわせて歌う。多くはレストランを兼ねているが、軽いお酒の席もある。 |
|
|
|
バイシャ(BAixa)のみどころ
●コメルシオ広場(Comercio)
|
1755年の震災で破壊されたマヌエル1世の宮殿があったところ。大航海時代の凱旋門。1908年にはカルロス1世と皇太子が暗殺されたところでもある。現在はバスと市電のターミナルにもなっている。 |
|
|
|
|
スペインに支配されていた民族の愛国心が、1640年ポルトガルの独立を勝ち取った記念広場。レスタウラドーレスとは「復興者たち」という意味。中央には高さ30mのオベリスクが建っている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4月25日橋を渡ったところに、高さ110mの巨大なキリスト像が建っている。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロのキリスト像を模擬して1959年に造られたもの。中にはエレベーターがあり、キリストの足元まで上ることができる。展望台からは、まるでリスボンの町がテージョ川に浮かんでいるように見える。 |
|
|
|
|
ヨーロッパの西のはずれ、大西洋に面した長い海岸線を持つポルトガルは、漁業の盛んな国である。市場には日本で見慣れた鰯、鯵、鯖、鯛や平目の他にも巨大な太刀魚から鮪まである。またアサリ、カキ、ムール貝などさまざまな魚介類が店頭に並ぶ。 |
|
|
|
|
|
|
































