リスボンの町とその周辺 ポルトガル(2)
![]()
 リスボンの中心部から西に約6km、テージョ川沿いのベレン地区は、ポルトガルの輝かしい大航海時代の遺産の地だ。当時、すでにユーラシアからアフリカに至る広大な海はアラブ人に交易路が網羅されていた。海外進出を夢見たエンリケ航海王子はインド航路を探り出そうとし、ポルトガルは未知の海へと船を漕ぎ出した。1498年、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路発見の偉業を成し遂げた。
リスボンの中心部から西に約6km、テージョ川沿いのベレン地区は、ポルトガルの輝かしい大航海時代の遺産の地だ。当時、すでにユーラシアからアフリカに至る広大な海はアラブ人に交易路が網羅されていた。海外進出を夢見たエンリケ航海王子はインド航路を探り出そうとし、ポルトガルは未知の海へと船を漕ぎ出した。1498年、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路発見の偉業を成し遂げた。
16世紀初頭、ヨーロッパの列強が争っている間、ポルトガルは新大陸ブラジルを併合、インドやマラッカ海峡を掌握し、太平洋への拠点を確保した。
こうして海外からもたらされた富によって栄華を極めた建造物がベレンにある。
新大陸に向けて船出して行ったベレンから西、大西洋の海辺を辿ると、かつては寂しい漁村にすぎなかった浜はいまポルトガルの大リゾート地となっている。
|
|
|
|
|
|
|
![]()
<コース>
リスボン(Lisboa)−ベレン(Belem)−エストリル(Estoril)−カスカイス(Cascais)
全行程 約30km
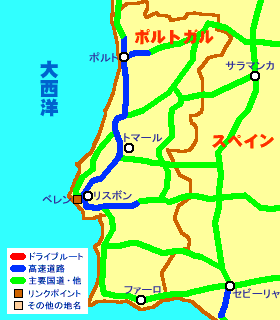
ベレン(Belem)のみどころ
●ジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jeronimos)
|
|
|
テージョ川の大河口沿いに、ヴァスコ・ダ・ガマのインド洋航路発見を記念して、当時の海洋王といわれたエンリケ王子が設計したという礼拝堂。その礼拝堂を基に1495年に即位したマヌエル一世によって造られた壮麗な建物。 |
|
この修道院の最大のみどころは、中庭を取り囲む約55m四方の回廊。石灰岩を用いた外柱やアーチには船のロープや貝など海にまつわるもの、花などをモチーフにした緻密な彫刻がほどこされている。 |
|
この壮大な建物の南門右手には、サンタ・マリア教会がある。修道院の名の由来ともなっている聖ジェロニモスの生涯を描いた彫刻や、その上部にはエンリケ航海王子の像がある。 |
|
|
|
●国立考古博物館(Mueeu Nacional de Arqueoiogia)
|
19世紀に修道院の西に増設された博物館で、ポルトガル各地や植民地などから集められたものが展示されている。大航海時代のポルトガルのコレクションで、珍しいものではブラジルの鳥の羽で作られたマスクやエジプトのミイラなどもある。 |
|
|
|
●発見のモニュメント(Padrao dos Descobrimentos)
|
1960年にエンリケ航海王子の500回忌を記念して造られたモニュメント。テージョ河口から大西洋に向かって、いまにも船出するかのような帆船をイメージした、高さ52mの記念碑だ。船首には、エンリケ航海王子が立ち、その後にはヴァスコ・ダ・ガマをはじめ、天文学者、宣教師、地質学者、詩人や船乗りなど、この時代に活躍した27人の偉人たちが続く。 |
|
|
|
|
1519年、海からの侵入者を見張るため、リスボンの西の砦として建てられた塔。マヌエル様式を代表する建物の一つでもある。海への出口に建つこの石造りの塔は、船乗りや旅人を迎え、二度と戻らない人々も見送ってきた。いまは2層の堡塁部分と4層の塔からなり、4階は「国王の間」であり最上階は王族の居室であった。そして、3階は兵器庫、2階は砲台で、1階は潮の干満を利用した水牢だった。 |
|
リスボンの西、テージョ川から大西洋に出たあたりの一帯は、コスタ・ド・ソル(太陽海岸)と呼ばれる大リゾート地だ。規模が小さいが、スペインのコスタ・デル・ソルとよく似たヨーロッパ有数のリゾート地。 |
|
|
|
|
古い建物が残るタマリス海岸の浜辺は、夏には海水浴客で賑わうが、ここ数年の間にテージョ川の汚染で海に入る人が少なくなったとか。 |
|
|
|
|
コスタ・ド・ソルの西の外れに位置する。古くは漁師町だったが、19世紀に王室一族の避暑地となってからは、貴族などの別荘も建ち、今日ではヨーロッパやアメリカからの観光客も多い有名なリゾート地となった。 |
|
|
|



















