 |
中欧の旅・ハンガリー

 ヨーロッパのほぼ中央に位置するハンガリーは、日本の国の約4分の1、人口約1,000万人の小さな国である。西部には“ハンガリーの海”と呼ばれる中欧最大の湖バラトン湖があり、温泉のあるリゾート地となっている。東北の山岳地帯の麓では、ハンガリー・ワインの大産地でもある。
ヨーロッパのほぼ中央に位置するハンガリーは、日本の国の約4分の1、人口約1,000万人の小さな国である。西部には“ハンガリーの海”と呼ばれる中欧最大の湖バラトン湖があり、温泉のあるリゾート地となっている。東北の山岳地帯の麓では、ハンガリー・ワインの大産地でもある。
変化に富む豊かな自然と、ローマ時代から幾多の民族、王国に翻弄されながら独自の文化を育んだ首都ブダペストは、ドナウ川をはさんで西岸をブダ、東岸をペスト地区がひとつになった“ドナウの真珠”あるいは“ドナウの薔薇”とも称えられ、ヨーロッパ屈指の美しい街である。
丘陵の多いブダ地区は丘の上に建つ旧王宮をはじめ、オスマン帝国時代をしのばせる遺跡が多い。丘の麓には薬用効果の高いことで知られる温泉が湧き、ローマ時代から人々の憩いの場であった浴場が市内に50ヶ所もある。
一方の平坦な土地が広がるペスト地区は国会議事堂、科学アカデミー、裁判所、美術館、国立博物館、大学などが集り、この二つの街を9つの橋が結ぶ。

<コース>
ブダペスト(Budapst)市内−エゲル(Eger)往復
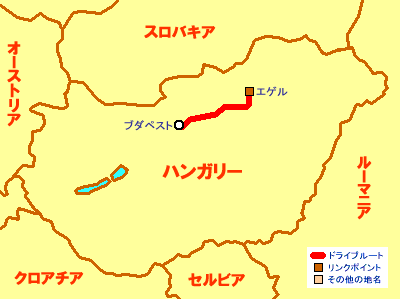
●ブダペスト(Budapst)
遊牧民を先祖とするハンガリー人は自らもマジャル民族と呼ぶ。13世紀にはタタール(モンゴル人)の来襲を受け、16世紀から約150年間、オスマン朝による占領時代、オーストリアとの二重帝国時代、さらに第二次世界大戦後ソビエト連邦時代には東欧圏に組み込まれるという歴史の変遷をたどりながらも、独自の歴史と文化を育んできた。
その首都ブダペスト市内を流れる川岸からの眺めは、まさに“ドナウの真珠”の名にふさわしい眺めだ。
|

ブダペストの真ん中を流れるドナウ川
|
ブダの中世の城壁に囲まれた王宮、ペスト側のゴシック建築の国会議事堂、二つの街をつなぐ9つの橋の中で10年の歳月をかけて、1849年ブダとペストを初めて徒歩で歩めるように結んだ橋が“鎖(くさり)橋”だ。ここから市内の観光名所を一回りするだけでも2〜3日は必要だ。
|
王宮(Budavari Palota)
ドナウ川に面した高さ約70mで南北に長さ約1.5kmの平坦な岩山に、中世から続く城壁に囲まれた歴代王の居城がある。13世紀にハンガリー王ベーラ4世によって初めて築かれた王宮だ。
その後増改築が行われ15世紀にはイタリアなどから職人や芸術家が多数集まり、王宮を中心に中欧のルネッサンスの中心地として栄華を誇ったが、16世紀オスマントルコ来襲によって壊滅した。
|

国立美術館のゲート
|

初代国王・聖イシュトヴァーン
|

骨董屋の洒落たサイン
|

焼き物も人気の土産品
|

土産物屋の店先
|

民族衣装の人形
|
●マーチャーシュ教会(Matyas templom)
ペスト側から王宮の丘を望むと高い尖塔が目につく。ブダペスト最大のみどころの一つだ。
13世紀に最初に王宮を建てたベーラ4世の命により、「聖処女マリア教会」としてロマネスク様式で建てられたが、14世紀にはゴシック様式に建て替えさせられ、15世紀には時の王マーチャーシュが塔を増築した。
だがトルコに占領されると、すぐフレスコ画などは塗り込められモスクとなった。
17世紀にトルコ支配から解放された後は、王宮と同じ運命を辿り、現在のゴシック様式の教会は戦後復元されたもの。
|

マーチャーシュ教会
|
教会の裏、王宮の城壁のように造られた「漁夫の砦」というネオロマネスク様式の砦風建築がある。ドナウ側を見下ろし、ペスト地区を一望するところに数個の尖塔と回廊からなっている。マーチャーシュ教会を改築した建築家による町の美化計画の一環として建造したもの。名前の由来はかつてはこの場の魚市場や、ドナウ川の漁師組合などがあったことから「漁夫の砦」という名がついた。
|

漁夫の砦
|

王宮内の漁夫の砦は観光客に人気
|
この王宮の丘は、一つの町になっていてレストランやみやげ物屋もあるが、北側には城門の「ウィーン門」という石のゲートがある。1936年、トルコからの解放250周年記念に造られたものだ。
|

王宮へのウィーン門
|

王宮内は街にもなっていて観光馬車や車も走る
|
●シナゴーグ(Synagogue)
ペスト側、デアーク(Deak)広場から東約300mのところに建つユダヤ教寺院。1859年に完成したヨーロッパ最大級のシナゴーグで、2つの塔のドームの高さは43mもある。広い内部には約3000の座席がある。ここではリストやサン・サーンスがオルガンを弾いていた。
|
礼拝堂の左側の建物は、ユダヤ民族の生活、歴史、宗教などに関する資料などが展示されている「展示舘」がある。
ブダペストには中世からユダヤ人のコミュニティがあり、19世紀後半にはバルカン半島から避難してきたユダヤ人が、シナゴ−グ周辺に暮らしていた。現在も教会近くにはユダヤ人が多く住み、独特の雰囲気がある。
|

ユダヤ人街の住居は頑丈な門の中にある
|
●温泉 ゲッレールト(Gellrt)

ドナウ河畔の温泉。堂々とした建物だ
|
ハンガリーは世界的にも有名な温泉国である。なかでもブダペストには100以上の源泉と50もの温泉施設がある。
ローマ時代、オスマン朝時代を彷彿させるような建物からスパを備えた温泉、医療を目的とした温泉とさまざまだ。
とくにブダペストの顔とまでいわれるゲッレールト温泉を体験してみたが、プールのように広い湯船?では、本当に泳いでいる人もいた。
|
1914から4年の歳月をかけて建てられたアールヌーヴォー様式の豪華な温泉で宿泊設備も完備している。内部にはイギリス・バースにあるローマ時代の遺跡のような石柱に囲まれた風呂。トルコ風呂に似た石造りのドーム型天井とアーチの出入り口のある風呂は、温度の異なる2つの湯舟や打たせ湯などがある。屋内外には温泉プールもある。
屋内の2つの湯舟のある風呂へは、男性はフンドシ、女性はエプロンをレンタルし、これを身につけて入る。ハンガリー式のルールの入浴法だ。
ここは男女別で、それぞれ脱衣所入り口で料金を払いフンドシやエプロンを借りてロッカーかキャビンに案内される。キャビンといっても1〜2人が着替えられるくらいの小さな空間だ。着替えたエプロンは前だけで後ろは裸だ。本来は日本のように皆裸で入ったようだ。
湯舟は通路をはさんで36度と38度という温めの湯。聞くところによると中には素っ裸もいれば水着の人も。もちろんエプロン姿の人もいた。日本人の風呂マナーのように、静かに湯に浸かるのではなく、湯舟の中を歩き回ったり裸のままで泳ぎ出す人までいた。なんとも滑稽な光景に思わず吹き出してしまったそうだ。
|

温泉のロビー
|

温水プール。隣には男女の大浴場がある
|
風呂上がりにはレストランで名物、ドナウ川産というナマズ料理を食べた。こってりと油の乗ったナマズをトマトソースと油で焼いたものだった。
味は悪くなかったが、油が強烈で少し湯あたりしていたせいか、食べきれなかった。
日本でもナマズ料理はあるが、ウナギほどポピュラーではないので、水郷や昔ながらのウナギ屋でないとメニューにはない。
|

ナマズは名物だが、脂が強烈
|
●エゲル(Eger)
首都ブダペストより東北東へ約130km、マートラ(Matra)とビュック(Bukk)の山々に囲まれた高原の町。堅固な城壁を持つエゲル城を中心に古い建物が多く残る町でもある。
近代化の波に取り残されたが、いま観光の町として脚光を浴びている。
またエゲルはハンガリー有数のワインの産地で“雄牛の血”という意味のエグリ・ビカヴェールが有名。
一方、温泉の町としても知られ、町の中にはウォータースライダーやジェットプールまである大きな温泉施設がある。
|

エゲルのバロック様式の教会
|
●エゲル城 (Eger・Castle)
13世紀に築城され、現在も町を望む丘の上に建つ城は多くの武勇伝が伝わる城として名高い。1552年トルコ人によって襲撃されたが、ときの城主ドボー・イシュトヴァーンの下で、ハンガリー軍がこの城に立てこもり、トルコ軍を追い返した。最終的には2度目の戦い(1596)でトルコ軍に敗れてしまうが40年余りもの間、町を守ったドボー・イシュトヴァーンは、いまでもエゲルだけでなくハンガリー国民のヒーローなのだ。
|

民族の英雄、ドボー・イシュトヴァーン(左手奥の像)と背後に建つエゲル城
写真提供:ハンガリー政府観光局
|

エゲル城のゲートでチケットを買う人の列
|

トルコと戦った英雄の像
|
現在、城壁の内部には13世紀の聖堂跡や15世紀の司教舘などが残る。この司教舘は博物館になっている。そこにはアートギャラリーや歴史的でき事を再現したものが展示されている。迷路のような地下要塞も観ることができる。
町の中心部、ドボー・イシュトヴァーン広場には、18世紀のプラハの建築家によって建てられたバロック様式の教会があり、トルコ軍と戦うイシュトヴァーンの像がある。
|

内庭の店への素朴な表示
|

土産物を売る
|
●美女の谷(Valler of the Beautiful Women)
エゲルの町の中心部から南西に約2km、ビュックの山々の麓、ワイン畑に囲まれた谷間が美女の谷だ。山をくりぬいて造った穴蔵の小さなワインセラーが70以上も並び、山肌の穴蔵の中には、酒場があり、前庭にはそれぞれ趣をこらしたレストランもあった。
小規模農家で作ったワインの旨さを競い合う小さなワインセラーには、大勢の観光客が試飲しながら、おしゃべりを楽しみ、そこへ数人のバイオリン弾きが加わって大騒ぎをするところもあった。あちこちで試飲をし酔いつぶれる者までいる。
ドライブ途中のドライバーは、くれぐれも誘惑には負けないように。
|

崖に横穴を掘った貯蔵庫が並ぶ(ワインの谷)
|

ワインの谷、貯蔵庫を改造した酒場
|
|
|
|
|