 =工事中=
=工事中=南ア・喜望峰~ノルウェー・ノルドキャップ(1972年の旅)
|
 振り返ると遥か昔の旅です。おおよそ半世紀前のアフリカ、北欧をコロナ・マークⅡで走ったのです。当時はマイカー時代到来の少し前で、若者は車を持つことに強いあこがれを持っていました。そんな時代ですから、海外ドライブは夢の世界で、国内ですら“日本一周ドライブ”などが、喝采を浴びていました。
振り返ると遥か昔の旅です。おおよそ半世紀前のアフリカ、北欧をコロナ・マークⅡで走ったのです。当時はマイカー時代到来の少し前で、若者は車を持つことに強いあこがれを持っていました。そんな時代ですから、海外ドライブは夢の世界で、国内ですら“日本一周ドライブ”などが、喝采を浴びていました。リスボン~コルカタ(カルカッタ)、オーストラリア一周、中東、イランの旅などを車で走り、レポートを書いてきた勢いで、南アからノルウェーの北端、ノルドキャップまで一気にドライブする企画を立てたのでした。会社勤めで記事を書いていたのですが、会社はよくもこんな無謀な旅を許してくれたと今更ながら思うのです。アフリカは日本人にとってまだまだ未知の世界で
 “暗黒大陸”などと言う言葉も、マスコミで使われることが珍しくはありませんでした。
“暗黒大陸”などと言う言葉も、マスコミで使われることが珍しくはありませんでした。アフリカの国々は、欧州列強の植民地から独立し始めているときで、まだまだ、植民地時代の名残は独立した国ですら、強く残っていました。
私は当時34歳。同行のカメラマン、中山広亮君は同期入社でした。車は当時のトヨタ自販が提供してくれましたが、ノーマルのマークⅡでした。当時は学術探検と称し、大学などが4輪駆動を調達し、数台で隊列を組んでの冒険・探検のようなドライブがある程度でした。マークⅡは横浜からモザンビークの首都、ロレンソマルケスへと船で送りました。受け取るために、スリランカ(入国d記は正論、出国はスリランカ)、インド洋のシェーシェル島、南ア経由でロレンソマルケスに入りました。
ホテルで船が着くのを待っているとき、日本赤軍の岡本公三がイスラエルのロッド空港で銃を乱射する事件がありました。前日まで楽しく話しをしていた宿泊客の白人達は、急に硬直した態度に変わったのが今でも印象に残ります。
アフリカ大陸を縦断してスペインへ入る計画でしたが、車が不調になったので、サハラ越えは諦め、ウガンダ、、コンゴ(当時サイール)、中央アフリカ、カメルーン、ナイジェリアのラゴスから、英国籍の貨物船に乗り、シエラレオネ、ガーナ等に寄港しながら、急にのんびりした旅になりました。グラスゴーに着き、フェリーでノルウェーのベルゲンへ渡り、北の果て、ノールキャップまでたどり着き、ベルギーへと戻り、約五ヶ月の旅を無事終えたのでした。(写真=上・喜望峰、右・ウガンダにある赤道の表示)
| 文・中島祥和 写真・中山広亮 |
4万キロの旅
 アフリカ大陸の最南端、ケープ・アグラス(南ア)を出たのは1972年の秋(五月)だった。赤道を越え、五ヶ月後にたどり着いたスカンジナビア半島の最北端、ノルド・キャップ=写真・左=もやはり秋だった。足としたコロナ・マークⅡの走行距離は三万㌔を超え、貨物船での航海も七千㌔を超えた。ヨーロッパのハイウェーを走り、古い町並み、城、きらびやかな都会。静かな北欧。ライン川、セーヌ川などの水は清らかとはほど遠かった。あふりかは自然が溢れていたが、国によっては独立後、首都の賑わいをよそに、地方では“原始”へ向かって、逆走((写真=左・ノルウェー皇太子の到達記念碑。右は方位表示とノルドカップ標識)している印象もあった。様々な体験をした五ヶ月の旅だった。
アフリカ大陸の最南端、ケープ・アグラス(南ア)を出たのは1972年の秋(五月)だった。赤道を越え、五ヶ月後にたどり着いたスカンジナビア半島の最北端、ノルド・キャップ=写真・左=もやはり秋だった。足としたコロナ・マークⅡの走行距離は三万㌔を超え、貨物船での航海も七千㌔を超えた。ヨーロッパのハイウェーを走り、古い町並み、城、きらびやかな都会。静かな北欧。ライン川、セーヌ川などの水は清らかとはほど遠かった。あふりかは自然が溢れていたが、国によっては独立後、首都の賑わいをよそに、地方では“原始”へ向かって、逆走((写真=左・ノルウェー皇太子の到達記念碑。右は方位表示とノルドカップ標識)している印象もあった。様々な体験をした五ヶ月の旅だった。激走に耐えたマークⅡと黒炭を示す表示。左はノルウエー皇太子到達記念碑
【注に替えて】1972年の旅なので、今(2024年)から50年余も前になる。撮影した写真は会社の資料部に保管されていたが、いつしか捨てられてしまった。私も切り抜きや写真を引っ越しが多かったのでなくしてしまい、今はいくらも無い。残念というか、お粗末というか…。中山君が個人で保存していたものをコピーして貰い、当時の記事を書き写す事にした。
アフリカ諸国は独立ブームとでも言えるように、イギリス、フランス、ポルトガル、ベルギー…、などの植民地から抜け出している最中だった。車を受け取ったモザンビークの首都ロレンソマルケスは、マプトと都市名が変わった。ナミビアは南西アフリカの名称だった。ジンバブエはローデシア、ベルギー領コンゴはザイールに変わり、再びコンゴとなっている。まだ、色濃く植民地時代の風習などが残っていて、外国人が被害に遭うような事は殆どなかった。銃の支配の名残だろうと思った。南アでは国境の税関、入国管理で「白人」「非白人」の窓口が異なっていた。日本人は「名誉白人」として扱われ、白人の窓口に並ぶことになっていた。振り返ると小馬鹿にされたような気もした。
(2015、2016、2019年に訪れたノルドキャップはすっかり変わって、大きな建物や地球儀をかたどったものなどが作られていて、そこへ入るには入場料が必要だった。72年にはもちろんそう言うものは無く、写真の記念碑はノルウェー、スウェーデン連合王国のオスカーⅡ世が1873年7月に岬に立った印です。ほかにはNのマークしか、ありませんでした。マークⅡで当時は岬の先端まで行けました。)
五ヶ月の旅を終わって

乾いたサバンナを、赤茶色のタンガ(体に巻き付ける布)をまとい、ヤリをかついだマサイの男が牛を追っていた。東アフリカの高原はゆるやかな丘が連なり、かなたには雪をかぶったキリマンジャロがぽっかりと浮かぶ。二、三戸の小屋があった。車をとめた。途端に女が丘を振り仰いで大声で叫んだ。枯れ草の斜面をタンガをはためかせ、ポッ、ポッと砂ぼこりをあげながら男がかけてきた。細い足、広い歩幅、しなやかで強靱な姿が、抜けるような乾期の空に美しかった。
右手にヤリ、刃渡りは1㍍はあろうという大物。きらめく穂先は圧倒的な迫力で近づいて来た。バサッとまといつくタンガが跳ね上げられ、男はヤリを握った右手を振りかざした。左手を横に開き、投げる構えに入りそう遠くではないところへと投げた。
競技のやり投げとは違う。遠くへ投げるのが彼らの生業ではない。槍が狙った獲物に突き刺さる距離が大切なのだ。遙か昔、サハラの北からブラックアフリカへ放牧しながら入り込んできたマサイ族は、ナイロビやダルエスサラームなど、東アフリカの大都会、近代文明に背を向けて、猛獣のたむろするサバンナで牛を追って生き続けている今は観光客に踊りを見せたり、立ち姿を写真にとらせたりして稼ぐマサイ族も多くなった。
ナクル(ケニア)の病院で日本人医師に会った。マサイの話しになるとこんなことを言った。
「輸血用の血液がなくなっちゃうんですよ。初めは不思議に思ったが、彼らの病室へ置いて目を離すと必ずなくなる。後で分かったんですが、のんじゃうんです」
牛の血液と乳を主食としている彼らは“病人食”ではとうてい満足出来ないのだろう。ライオンに食いつかれたり、引っかかれたり、肋骨をサイに突かれてパラリパラリと折られた者もいるという。ヤリ一本で立ち向かうなどと云うことは、遠い昔の話しだと思っていたが、医師は約半年間におわたる外傷者のカルテをめくり、その証拠を見せてくれた。
✕ ✕ ✕ ✕ ✕

コンゴ川の支流(中央アフリカ)
南ア、ローデシアに代表されるホワイト・アフリカ、ナイロビを中心とする東アフリカ(ブラック・アフリカ)は、さらりと見る限り、動物の住む快適なサバンナであり、文明と自然のマッチした美しいアフリカである。しかし、そこですらメーンルートを外れると原始の香りがする。ウガンダ国境からルウェンゾリの麓を越え、ザイール(旧ベルギー領コンゴ)に入ると、もう様相は一変する。熱帯雨林、ジャングルの中の橋は落ち、巨大なコンゴ川の支流のいくつかにあったフェリーボートは、動かなくなったり、沈んだりしていた。
丸木舟を数隻組み合わせ、人足を集めて車をのせ、手こぎで渡ることになる。コンゴから中央アフリカへ入るには、フェリーが壊れて半ば沈んでいて、幅三百㍍ほどの川が越せないため、千㌔も悪路を迂回しなければならなかった。
夜になると真っ暗闇の部落からタムタムが響く奥地では、いつ通るともしれない旅人を目当てに自分たちがとったサル、シカのたぐいを棒の先にぶらさげて売っていたりする。殆ど売れないから腐る前に本人が食うにちがいない。
こんな村はずれのやみのジャングルの中に、デートの二人連れの光る目と白い歯だけがヘッドライトに浮き上がることがあった。なにがひそんでいるかわからないジャングルをデートの場に選ぶことはあるまいと考えるのは、余計なお世話というものだろう。
✕ ✕ ✕ ✕ ✕

五月のケープタウンは街のすぐ北側にそびえる写真・上=が、深紅の夕焼けの中に、焦げたように突き出していた。間もなく夜が来て、南十字星が青みの残る空に、にじみ出た。ザイールの雨季のジャングルの太陽は、湿気にかすみ、真昼でもオレンジ色で、深い雲と黒い木々のすき間からときおり顔を出した。
そして、ツンドラが続く極北の地、ノルドカップでは、金色に輝く夕暮れのあと、けんらんたるオーロラが天空をおおった。宇宙からの原子が大気に突入して発する放電は、神々しいほどに美しく、もう冬のやって来ている北極圏の夜の寒さや、長かった旅の疲れを忘れさせてくれた。
すべてがめまぐるしく変わった。しかし、五ヶ月の旅は、そうした変化する環境に、すっかり私を慣れさせてしまった。移動することが日常化し、生活のリズムに変わるころ旅は終わったのだった。
(写真はいずれも当時・報知新聞社写真部員、中山広亮撮影)
1)旅の始まり

柔らかくよどんだような川には、満月が反射していた。フェリーボートが対岸からやってくるのを待って,ぼんやりと黒い椰子の葉と銀色に輝く水をながめていた。哀調をおびた歌声が流れてきた。大勢で歌いながら,船着き場に歩いてくるようだった。ボートが着くとその歌声の集団は、はだしで軽いステップを踏みながら桟橋を渡った。
約十人ほどの女。白い布を巻きつけ、中には子供を腰のところでおぶっている者もいた。古いヂーゼル・エンジンが、船体を突き上げはじめ、ゆらりとワニのすむ川へに乗り出しても、女達の歌声は続いた。南ア出身の歌手マケバ(国籍はアメリカ)の“パタパタ”と、とてもよく似たリズム。一人が素晴らしく通る声をあげると、それに他の女達が合わせた。突然、音階が変わる。みんながそれにならう。
黒い肌の女達が、電灯もない渡し船の上で,月の光に白い布をひらめかせ,ひょい、ひょい、と尻を突き出すしなやかな動きは,幻想的でもあった。破れズボン、シャツ姿の“船頭”に何の歌かと尋ねたら,苦笑いしながら答えた。
「たいした意味じゃない。結婚式に呼ばれ、酔っ払って騒いでいるだけさ」
どうも歌の文句は、外国人に説明するには具合の悪いものだったようだ。
対岸に着いても、彼女たちは歌い続け、再び桟橋を強く踏みならして拍子を取った。白い衣の一団はアカシアと椰子の木の間へと細い踏み跡をたどり、歌声とともに消えていった。
スリランカ(セイロン)、セイシェルズ、ナイロビとインド洋を飛び石伝い。ヨハネスブルグを経由してロレンソマルケス(モザンビーク)へ入った。日本から送った車が着くのを待つ間、借りた車であちこちを走り回り、やっと出会った“アフリカ”だった。モザンビーク―。ポルトガルの海外州。首都ロレンソマルケスは近代的なビルが建ち並び,整備された海岸沿いの道路は、椰子の並木が美しい。着飾った黒人達がポルトガル人とともに街をゆく。
中心地、シティーホール前の広場には、原住民を馬の蹄にかけ、銃で撃ち倒すポルトガル兵士のモニュメント。酋長らしき男が縄で縛られ、将軍の前で首をうなだれるシーンも、浮き彫りにされていた。それらの原住民の子孫としか見えない人々が、無表情に周囲の芝を刈り、家族連れはフト見上げて通り過ぎて行く。
どう思うかとスタイルの良い黒人青年に尋ねたら「昔の事だろ」と素っ気ない返事だった。
この町は“異国”だった。ポルトガルからやって来た人々は、毎日午後五時に、リスボンへ向かって飛び立つ旅客機を懐かしそうに眺める。

(当時、南ア入りにはセイロン経由が便利だった。入国はセイロン、翌日はスリランカに国名変更された)
「リスボンは良いところだ。行ってみるがいい素晴らしい街だ」
こんな話を何度も聞いた。モザンビーク、六百六十万人の総人口のうち、黒人が六百四十三万。黒人以外はヨーロッパ人、中国人、インド人を含めて約十五万。ポルトガル人はそのうちの九万人を占めているに過ぎない。都市に集中する白人達。ロレンソマルケスは、誰にとっても尻の落ち着かない街なのかも知れない。
舗装された郊外の道路。バスを待つ女の子が,一人で何かを口ずさみ、腰を振って踊っていた。裸足の女が、頭の上に荷物を載せて、ハイウェーをてくてく歩いていた。郊外のマーケットは、ちょっと怯むほどの熱気があった。こんなとき、アフリカの旅が始まったんだ,と思った。
2)車が無事に到着。カニとエビで祝う
高台にあるホテルから、ロレンソマルケスの街が見渡せる。日本からの車を積み込んだ船は、もう十日間も岸壁の空くのを沖で待っていた.船会社へ日参して尋ねるたびに、帰ってくる答えは決まっていた。
「明日か,明後日。そう、三日も待てば必ず入る」-。
ラテン系の人々に共通する“おおらかさ”かも知れないが、まだか,まだかと“旅の足”を待つ者にとってみれば、彼らには言われないことなのだが「怠けやがって」とでも言いたくなるいらただしさがある。

「船は見えるか」
「何隻か来ているよ」
「よし、望遠を頼む。船名を読もう」
中山君の持って行った300㍉の望遠レンズは、リングをセットすると600㍉の倍率にかわる。これで港へ入ってくる船の名を読もうというわけだ。狙いは“STRAAT ARGOA”。オランダ船籍だ。
「違うな」
「よし、オレにも見せてくれ」
こんなやりとりが続いた。オランダ国旗とその船の名は、いつまでも現れなかった。だから十三日目の朝、船会社で「今日の夕方、岸壁のスペースが取れたから接岸する」と言われても、とうてい信用出来ないのだった。
騙されるのを承知でホテルへ飛んで帰った。さっそく望遠をセットし、右目がぼんやりとしてくるまで、レンズを覗き続けた、船はのろのろと入ってきた。午後一時。たしかに"STRAAT ARGOA”の文字が読めた。いったんストップした船は、うれしいことに再び動き出して倉庫群のカゲに消えた。もちろん港へ直行である。税関はうるさくないが、車を降ろすときに落とされないか、などと心配していたが,無事に夕方受け取ることが出来た。損害と言えば私の下着五枚、ズボン一本、靴下五足。中山君は新品の厚手のセーター、靴下を四、五枚抜かれたことくらいだった。後になって悔しがるのだが、このときはいっこうに気にならなかった。
強い横風の海岸通りで頃なのテスト走行とシャレた。荷物やガソリンなどを、あちこちと積み替えて走り回った。憎らしかったロレンソマルケスの遠浅の海は、黄色っぽい砂が沖の波打ち際まで、しま模様を作っていた。
チコというカニの仲買人に会ったのは,この海岸だった。黒人達は働く。白人達も働いているに違いないが、ヨット、モーターボートに乗って海を走り,岸壁から糸を垂らしているのは白人たちだった。チコと称する男は、頭に水のしたたる籠をのせていた。腰でバランスをとり、地引き網が引き上げられたところや、舟の着いた場所をひょひょこと軽快に渡り歩いていた。私の立っているすぐ近くでは、真夏の太陽の下で、老婆が椰子の葉で編んだカゴに,数匹のカニを入れてチコの来るのを待っていた。
「二十エスクード(約二百円)くれよ。オレの写真を撮るなら…」チコは抜け目なく、モデル代をせびる。値切って半額にさせたが、それでもこの地では高額と言うべきだろう。チコは老婆からカニを受け取り、足をパチパチと折って、ハサミの付け根に差し込んだ。それでカニはハサミを動かせなくなった。チコは老婆に八匹のカニ代金、二十五エスクード(約二百五十円)払った。写真代はずいぶんとふっかけたものだ。
ロレンソマルケスでの最後の夜、たらふくカニとエビを食った。車エビは一㌔二百五十円。カニはかなり大きな奴でも二百円はしなかったが、海岸に比べるとべらぼうな値段だ。いらいらと車を待っていた時の気持ちはすっかり治まった。いよいよ“旅立ち”だ。
3)親切な人達
「ドルで払うよ」
「いや、ランドじゃないと駄目だ」
「ここに御銀行がないんじゃ、ランドを買いようもないよ」
「モザンビークの税関の所に銀行がある。そこで替えればいい」
さて、弱った.やっと手に入れたマークⅡを飛ばしてモザンビークを出国、コマチプールトの村にある南アのゲートをくぐったのに、税関、出入国管理事務所の庭で、頭を抱えることになった。南アの自動車保険はランドを支払わないと加入できないのである。何しろ銀行のあるモザンビークを出国してしまったし、南アでも早々と入国スタンプをぺたんと押されている.うっかり戻ったら、それっきりニュートラルゾーンから出られないことにもなる。進退窮まった感じ.しかし、入国管理官はにやりとしてわら半紙にスタンプを押していった。

ロレンソマルケスの漁港
「もう一度、モザンビークを見物して来なさい。これは臨時の出入国証。こことモザンビークの間は保険無しで走ってもいいよ」
おかげで無事にランドを手に入れて南アへ再入国である。荷物のチェックもあっさりしたものだった。実はパスポートチェックを受けるためドアを押そうとしてびっくりした。二つのドアがあり
「WHITE」
「NON WHITE」
の文字が書かれている。あらかじめこうしたもののあることは知っていたが、目の前にそれが出てくると、やはり複雑な気持ちになるものだ。(1972年当時です)
人種差別という先入観があるからなおされだ。悪い印象というものは強烈なもので、うっかりすると、悪辣な人間ばかりが集まっているような気になってしまい、ちょっと引っかかるが、車を歯h知らせているうちにやはり気にすることはないことがはっきりしてきた。道をたずねたスタンドのオヤジは町外れまでわざわざついてきてくれたし、プレトリアの警官はもっと楽しかった。
「駐車場はありませんかね」と尋ねた。その場所は駐車禁止だった。
「どこから来た?」
「東京。今日はロレンソマルケスから走ってきた」
「よし、ちょっと待て」
すぐそばに駐まっていた運転手に近づいた。なにやら文句をつけているようだった。しぶしぶ小型トラックは走り去った。
「車がでたところへ駐めろ」
「だって、そこは駐車禁止でしょう」
「ワシが決める。次に来るときにはワシにもこんな車を一台持って来てくれよ」とウィンクしてどこかへ行った。
一時間ほどして戻って来たら、すぐ後ろに駐まっていた車のフロントグラスには、べたっと駐車違反のステッカー。もちろん我らは無事だった。しゃれっ気のある警官である。商店にはいったとたんに、オヤジに言われた。
「国籍はどこだ」
「日本」
「日本の何処だ」
「東京」
ちょっとぶっきらぼうに答えた。
「よーし、トウキョー ジャパン ベリーグッド」
何だか分からないけれど、オヤジさんは盛んに喜んで、グレープフルーツを五個ほどくれた。
差別されるかどうか、それはもう個人の問題であろう。薄汚い格好をして一流ホテルへ転がり込めば、日本のホテルだってフロントはすげなく断る。
「ただ今満員で御座います」
まして外国人なら尚更であろう。いくつもの国を旅するものにとって、へたな先入観を持つのは不幸だ。(写真はケープタウン西方の高台)
【注】モザンビークから南アへ入国したが、当時のローデシアのビザ取得や、南アを旅した記録があると、当時南アはアパルトヘイト政策をとっていたので、入国拒否をされる国もあるといわれた。南アのビザを別紙で貰ったり、パスポートの問題もあった。また、車の整備もあり一旦首都、プレトリアへ行った。その後、ケープタウン、ケーアグラスと南アの最南端まで走り、再び北上することになった。
4)最南端の岬へ

ヨハネスブルグから南西にのびる国道9号線に走り出たのは深夜の二時半。買うダイナサバンナや、小さな町を抜け、昼が過ぎ夕闇が迫る頃、道は山岳部をくねっていた。滝、岩盤、盆地―。中央部の淡々としたくねりは、南へ来て圧縮されたような山並みに変わっていた。走り始めてからメーターは千五百㌔になろうとしていた。そんなときに峠はひょっこりとあらわれた。ゆるい岩の尾根を回り込んだ時だった。
よく鮮血のような夕焼け、というが、まさにそれ。途中からひろったプレトリア大学工学部の学生、ジョーンズ君は助手席で大声を挙げた。
「ラッキー。いいタイミングだ。最高!」
見下ろす谷間の町はもう夕闇が来て、灯がまたたいていた。その向かいの黒い山並みの上は、息を吞む色彩で刻々と変化していた。私がリアシートからカメラをひきだすころには、色はもう、だいぶ黒ずんでしまっていた。時間を忘れさせる夕暮れは、、南アの土地の美しさが集約された感じだった。
五人の男が道の左側を変な格好をしながら歩いて来た。先頭の男は、古い言い方をすれば“五球スーパー”とでも言うほかない旧式のラジオを首からぶら下げていた。大きなバッテリーが入っていて重いだろうにと思うが、彼らはそんなことには一向にお構いなく、ボリュームを一杯に上げていた。
リズムに合わせて陽気にステップを踏み、腰をくねらせ、歌いながら腕も動かしていた。喜望峰への道で出会った黒人のグループだった。ケープタウンへの途中、百五十㌔ほど乗せた老黒人は、私が車をとめると、息せき切って駆けつけ「旦那、旅行の許可証は持っている。息子のいる町までぜひ乗せて行って下さい」とすがるように頼み込んだ。彼は止まる車を三日間待っていた。道端に立って三日目の六時間が経ったところだと彼は言った。
白人青年がひょいひょいとヒッチハイクで移動するのを知っていると、いささか哀れみも感じるが、道ばたで手を挙げている男を、乗せるかのせないかは、ドライバーの勝手で、不公平だと文句を付ける筋合いではなかろう。そう思わせたのは、楽しそうに踊っている黒人達と出会ったからかも知れない。
厳密に言うと喜望峰はアフリカ大陸の最南端ではない。約二百㌔ほど東によったケープアグラスにアフリカ大陸最南端があるJ。しかし、アグラス岬は緩い傾斜の荒れ地で、ズルズルと海へのめり込み、陸地が海に降参しているようになっているのに比べて、喜望峰は勇ましい。岩尾根が海へ突き出し、岩壁がインド洋と大西洋の波をタチ切っていた。“最南端”にふさわしい豪快さである。

アフリカ大陸最南端、喜望峰の東、20㌔ほどだったか…
岬の半分ほどは公園になっていて、入園料を支払う。さらに先端の山の手前で車を降りる。二百㍍ほどの坂にマイクロバスがあって、南の果てを見物する仕掛けになっていた。午前中だったのでインド洋が光り、大西洋は深い青だった。ダーバンやケープタウンで、インド人や学生が差別反対のデモをくりかえしていたが、ここにはインド人の団体がバスでやって来ていた。
東方を備え付けの望遠鏡で覗いているインド人に「どこを見ているんだ」とたずねた。
「きれいだからさ。船が一つ見えるぜ」
余計な詮索はやめることにした.旅人は、南の果ての風景をたっぷりと楽しむにかぎる。

ケープタウンをカラ身で往復し、ヨハネスブルグへ帰ってきた私は、車の最終的なチェックに取りかかった。北へ向かう旅は、広大なサバンナに始まって、巨大なコンゴ川流域の雨季の熱帯雨林、夏のサハラ砂漠、さらに極北のツンドラなど、あらゆる自然条件が横たわっていた。常識的にこうした長い旅をたった一台の車、しかも乗用車でやった例はない。四輪駆動と乗用車のコンビ、または数台でキャラバンを組むのが普通だ。
「よく乗用車一台で行く気になるなー」と南アに住む日本人に言われたこともあった。
マークⅡはまったくスタンダードのままだった。かわったところといえば、トランクの中の、スペアタイヤのスペースを40㍑の補助ガソリンタンクにかえ、オイルパンの下に鉄製のアンダーガードを取り付けたくらいのものだった。理由は簡単である.下手にいじって車のバランスを崩すより。市販のままの方がいいだろうと、考えたからだった。エンジンも六気筒はやめ、単純な四気筒の方を選んだ。
ケープタウンへ行く前に、あらかじめ中門して置いたルーフキャリアを取り付けた。オランダから移民してきた技術者は得意そうに寸法を測って作っ特製のキャリアを自信たっぷりに説明した。
「二百五十㌔までは保証する。うちはルーフキャリア専門だよ。たとえ車がつぶれてもこいつはちゃんと屋根に載っかっているいるはずだ」
昨年、オーストラリアを旅したとき、シドニーで市販のものを買った。タイヤを二本載せ一ヶ月のたたないうちにこわれてしまった。二台で走っていたので、荷物の割り振りはなんとかなったが、今度はすべてを一台でこなさなければならない。砂漠を往くか、ジャングルを選ぶか、その直前に決めるけれど、サハラには千二百㌔も給油出来ない地域があるし、ザイールの悪路は動きのままならないことも分かっていた。奥地でタイヤ、ガソリンのスペアを失うことは、旅の終わりであり、命にもかかわる。
 屋根に積む荷物は、最大百キロそこそこで治まる計算だった。だからルーフキャリアを取り付けた男の自信ありげな言葉は、たいそううれしかった。もっとも、後でやはり壊れた。東アフリカのサバンナで、ブレーキを踏んだとき、想定していたボルトがはずれて前へずれ、危うくフロントガラスをブチ破るところだった。パンク修理のセット、足踏み式の空気入れも積み込んだ。スペアのタイヤ、チューブを二本ずつ持っていたが、ちょっと心細い気がしたからだった。結局これはパンクして立ち往生していたバイクを修理してやったほかには、トランクの中にころがっていた。
屋根に積む荷物は、最大百キロそこそこで治まる計算だった。だからルーフキャリアを取り付けた男の自信ありげな言葉は、たいそううれしかった。もっとも、後でやはり壊れた。東アフリカのサバンナで、ブレーキを踏んだとき、想定していたボルトがはずれて前へずれ、危うくフロントガラスをブチ破るところだった。パンク修理のセット、足踏み式の空気入れも積み込んだ。スペアのタイヤ、チューブを二本ずつ持っていたが、ちょっと心細い気がしたからだった。結局これはパンクして立ち往生していたバイクを修理してやったほかには、トランクの中にころがっていた。装備はOKとなった。そこでいっちょう日の丸でも付けるかということになった。あちこちで「チャイニーズか」とたずねられ、「いや、日本人だ」と答えて話に入るよりも、国旗を付けておけば簡単だろう、と考えたのだった。プレトリアの日本領事館で、廃棄処分するものを譲り受け、得意になって縛り付けた。しかし、振り返ってみれば、日の丸が日本の国旗だという事が、相手に分かるかどうか、保証の限りではない。
「中国人?」
「いや、日本人」
そんなやりとりは、その後も繰り返されルのだから…。私たちの車は、綺麗に整ったプレトリアの市街を抜け、ローデシアへの道をたどった。
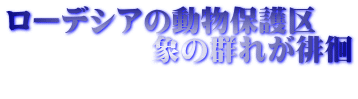

太陽はサバンナを黄色っぽく染めていた.草食動物をたっぷりとながめ、宿へ帰ろうとゆっくりと車を走らせているときだった。数頭の象がのんびりと前方を左から右に横切った。さらに車を進めた。と、また前方にでっかいやつがのっそりと藪から出て来た。五十㍍ほど先である。怒らしちゃいけない瘏車をとめた。左手のヤブがざわざわと鳴った。赤い太陽が黒光りする象の丸っこい背中、頭、鼻などをシルエットで浮かび上がらせた。四つ、五つ、七つ…。バックミラーにも道路に降りた象が映っていた。
ローデシアの西部にあるワンキー・ナショナルパークでのこと。
「逆行で象を撮ったらきれいだろう」などと話ながら、群れを探していた。あらわれたのは絶好のシーンだが、白状すると数が多すぎ道をふさがれ、そんな余裕はいっぺんに吹っ飛んでしまった。
圧倒的な重量感のある奴が五㍍ほど先をうさんくさそうに通り過ぎる。首をすくめて後ろを見ると、巨大な尻にひょろりと短い尻尾が垂れている。象の群れは車などをいっこうに気にせず、悠々と自分たちの通路を移動していた。
「刺激しちゃまずい」と思い、もうエンジンまで切って息をひそめた。冷や汗である。動物の習性をよく知っている人にとって、この仕草はお笑いかも知れないが、はじめて群れの中にはいった感じは、おっかないの一語につき、ナショナルパークのゲートにあった注意書きを思い出した。それは髑髏にぶっ違いの骨。いわゆる“海賊マーク”の大きな奴が書いてあり、その下にこう続く。
「車から出るな。道路に沿って走れ」
これに反したら命の保証はしないといういみかが、髑髏のマークとなっていた。
 象は十分ほどで“囲み”を解いた。移動していったのである。もうゲートへ向かって一目散。残った三十キロほどのゲートへの道が、やたらと遠く感じたものだった.パンフレットの説明や写真は、一般的にこけおどしが多い。期待すればするほど裏切られるのが常識だが、ワンキーではそれが控え目すぎる。
象は十分ほどで“囲み”を解いた。移動していったのである。もうゲートへ向かって一目散。残った三十キロほどのゲートへの道が、やたらと遠く感じたものだった.パンフレットの説明や写真は、一般的にこけおどしが多い。期待すればするほど裏切られるのが常識だが、ワンキーではそれが控え目すぎる。陽が傾く頃になると、水場に動物たちが集まってくる。キリンが長い足を開き、首をコンパスのように突き出して水を飲む。アンテロープ類やシマ馬は、ピリピリと神経質に辺りをうかがいながら、群れをなしてやってくる。もっそりとオス象が一頭、また一頭と姿を見せてはサバンナへ消えて行く。水場の近くに陣取っているうちに、いつの間にかそうした動物たちと、人間の間に何か約束事でもできあがって、決して危険は無いというような錯覚に陥る。動物園のオリをを隔ててしかそうした動物と接した事のない人間は、フト間にオリがあるような気にもなる。(右は原住民の聖地、ジンバブエの遺跡)
「ゲートとを出るのは午後六時まで。それに遅れないようにして下さい。遅れると捜索隊が出て、捜索費を請求されますよ」
ホテルのフロントが言っていた言葉も、象の群れに囲まれるまでは、下らない冗談くらいに聞き流していたが、なるほど、あそこでぶつけでもしたら、それっきりの事は確かだ。もっとも、後からケニアで動物を追い回して、ゾッとしたケースに比べると、象の群れを、それほど怖がることはなかったのだが…。
7)悪魔の滝・ビクトリア・フォール
 地平線まで広がるサバンナのなかに、一カ所だけ“雲”がわき上がっていた。そこがビクトリア・フォールだった。滝つぼからのしぶきが、氷柱のように舞い上がり、十㌔も離れると、雲が吹き出すように見えるのだった。滝と言うと山の急斜面を連想するが“対岸”との高度差は殆どない。緩やかにサバンナをうねってきたザンベジ川が突然、足元をすくわれるように岩の割れ目に落ち込んでいた。この滝の発見者、リビングストンの像のあたりは、風向きによってはメーン・フォールも見えると聞いたが、足元に落ち込む“悪魔の滝”の他は見通せない。百㍍ほどの割れ目の間から吹き出すおびただしい“雨”で、あの辺りだな、と思うほかないのだった。
地平線まで広がるサバンナのなかに、一カ所だけ“雲”がわき上がっていた。そこがビクトリア・フォールだった。滝つぼからのしぶきが、氷柱のように舞い上がり、十㌔も離れると、雲が吹き出すように見えるのだった。滝と言うと山の急斜面を連想するが“対岸”との高度差は殆どない。緩やかにサバンナをうねってきたザンベジ川が突然、足元をすくわれるように岩の割れ目に落ち込んでいた。この滝の発見者、リビングストンの像のあたりは、風向きによってはメーン・フォールも見えると聞いたが、足元に落ち込む“悪魔の滝”の他は見通せない。百㍍ほどの割れ目の間から吹き出すおびただしい“雨”で、あの辺りだな、と思うほかないのだった。「ここじゃ滝が見えないでしょう。向こうへ歩いて行けば、メーン・フォールが素晴らしいよ」と親切に教えてくれた老夫婦は、r-ンコートを着て、カサまで持っているのに、全身びしょ濡れだった。
高さ約百八㍍、幅千八百㍍。乾いたさばんなは、ひっきりなしのしぶきで、この滝の辺りだけはジャングルになっていた。細い道をたどってメーン・フォールの向かい側へまわる。スコールのようにしたから雨が降りかかる。風が去ると舞い上がったしぶきが、今度は上からドッとくる。
「カメラが使い物にならなくなるよ」
コートをカメラに巻きつけた中山君がぼやいた。
囲いも何にもない。ストンと切れ落ちた滝つぼのふちまで誰でも行ける。ツルリと足を滑らせたら、先ず絶対に助からない。日本ならさしずめ「危険、立ち入り禁止」になっているはずの、しぶきでぬるりと滑るあたりには、ちょっと注意を引くために、木の小枝が放り出されているだけだった。
「滝へ落ちる人はいないかね」とホテルの女主人にたずねた。やっぱりそうか、と言う返事だった。
「あまり近づかない方がいいですよ。三週間前にまた一人落ちたから…」
霧ごしに覗いた滝つぼは、熱湯がたぎるように泡立ち、盛り上がっていた。
あとで見たザンビアの観光ポスターは、滝の落ち口の岩の上で、三人の青年が遊んでいる写真だった。これじゃ落ちるやつも出てくるわけだ、と思った。危険とか安全とか言う考え方の基準が日本人とはかなり違っていると言わざるを得ない。砂漠へオートバイやおんぼろ車で乗り出すのを、フランス人はちっとも止めない。日本では待ったの掛かる小さなヨットで外洋へ乗り出すのもイギリスではヒーロー、オーストラリアではサメのいる海を護衛の船もなしに泳いで島へと渡る冒険者を褒めあげ、一人が食われ、一人が命からがら逃げ帰っても、別に非難はされない。

「本人自身の問題である」という強い個人主義、個人の意思を尊重する伝統があるのだ。
「毎年、何人かは滝つぼへ落ちる」
それならば、日本では大問題になるが、危険かどうかは、大人が自分で判断すればいいもの、というわけだ。“過保護青年”タチには、いささかきついかも知れないが…。
シリがムズムズするような滝つぼのぞきのあと、おんぼろのセスナ機をチャーターした。十五分間で三千円ほど。高いけれど観光地では仕方がないのでOKした。ガタガタの飛行機は、滝の真上には近づけない。しぶきの“雲”がすぐ近くまで来ると、激しく揺れた。パイロットはあっさり遠ざかった。サバンナの広い幅でのたくってきたザンベジ川は、滝を境にして、今度はそこだけ深く狭いミゾとなって流れていた。
| 【注】◇ローデシア 旅した当時のローデシアは、人種差別問題の非難を浴びて、国際的に孤立していた。国連の経済制裁に伴い、日本総領事館(そるすべりー)はじめ、世界各国の公館が閉鎖され、事実上国交が断たれていた。イギリスは東アフリカの植民地支配の最後の拠点として、一九五三年、ローデシアを中心とした中央アフリカ連邦を結成したが、民族解放運動が高まり、北ローデシアはザンビアとして、ニアザランドもマラウイとして独立、南ローデシアだけが残った。 四百万人の黒人に対して、二十二万人の白人が結成した自治政権が一九六五年ローデシアとして独立宣言。七〇年には白人優位の共和制に移行して、アフリカ諸国の非難をいっそう高めた。(これは旅した当時の状況。今はローデシアは無く、一九八〇年ジンバブエとして独立している) |
8)ザンビアの税関で
「ドルを持っていますか」
「持ってます」
「それでは申告して下さい。なるべくこまかく…」
ローデシアから橋を渡っていよいよ“ブラックアフリカ”へはいったザンビアの税関である。申告用紙に記入して渡した。
「では、そのお金とトラベラーズ・チェックを見せて下さい」
「エッ、お金を見せるの?」
「一㌦札まで、全部出して下さい」
税関の黒人は、意地悪そうな目つきに変わっていく。
私はナイロンチャックをつけた布製の袋をハラに巻き付けていた。昔の表現をすれば“胴巻き”である。旅で金をなくすほど悲劇はないから、それこそ肌身離さずである。ひょいとシャツをめくって金を引き出した。中山君があわてた。首からキンチャク型の袋を両脇にぶら下げていた。片方は現金。もう一つは”お守り”である。ぶら下げると上がキュッと閉まる巾着袋だから、シャツを脱がないと出せない。あわててトイレへ走ることとなった。
税関吏は一枚々々ていねいに札を数えた。一般的に現金を調べるといっても、高額紙幣やトラベラースチェックをパラパラとみて、あらかじめの額を読み取るのがプロというものだ。そこまでやる国も、相手が日本人だと殆どしないといっていい。それが、ここは本当に丁寧に一枚ずつめくった。
「申告が違ってるぞ。どういうわけだ」
やれやれ、いらっしゃいましたか、である。これまで五十数カ国を陸路で移動してきたが一㌦のはてまでかぞえたすえ、十㌦にも満たない申告ミスに文句をつけられたためしがない。だいたい、余程神経質な人でも、長い旅のあいだ中、所持金をきっちりは覚えていないだろう。もうはらをすえた。申告漏れの八㌦を“没収”されるのもやむを得ないと思って言った。
「申告し直しましょう。あなたの数えたとおりに…。もし駄目ならその分はあきらめましょう」
開き直りである。相手もしぶしぶ認めてはくれたが、荷物調べは厳重をきわめ、一時間以上もトランクをひっくりかえされることとなった。
 もっとも、外貨不足に悩むザンビアは、㌦の持ち出しに厳しい。外務省関係の日本人看護婦は、空港の係員がいないため、申告せずに入国した。出る時チェックされて、なんと五百㌦没収された例がある。むしろじっくり時間をかけて、札を勘定してくれた税関吏に感謝しなければなるまい。
もっとも、外貨不足に悩むザンビアは、㌦の持ち出しに厳しい。外務省関係の日本人看護婦は、空港の係員がいないため、申告せずに入国した。出る時チェックされて、なんと五百㌦没収された例がある。むしろじっくり時間をかけて、札を勘定してくれた税関吏に感謝しなければなるまい。私はブラックアフリカへやって来たことをしみじみと感じた。政治とか思想とかを抜きにして、こうしたチェックは旅人にとって。面倒だし、つらい。
ローデシアからザンベジ川を渡ったとたんに、はっきり言って世の中が変わったのである。かつて“北ローデシア”と言われた時代に栄えたリビングストンの町は、ひっそりとしていた。広い道路の真ん中に植えられた花が、かえってさびしい。泊まった町外れのホテルは、窓にがんじょうな鉄格子のはまった広い部屋がいくつもあったが、電気はつかず、お湯も出なかった。自然公園の案内があったので立ち寄ったが、動物が保護されているのかどうか、ブッシュばかりで、ゾウ一頭みられなかった。
9)探検家・リビングストン最期の地

「ドクター・リビングストン」
ジャングルの中の草だらけの小道を、はだしでスタスタと歩いて案内してくれた二人の少年が、得意そうに指さした。夕方でグッと傾いた太陽は、木の幹を赤く染め、モニュメントを浮き立たせていた。アフリカ探検史に偉大な足跡を残したリビングストンが、ナイル川の源流を探し当てられないまま死んだのがこの場所だった。
誰にでも知られているこの探検家の最期の場所を訪ねて見ることを、ザンビアに入ったときから一つの目標にしていた。モザンビークの奥地、コンゴの奥地と言われてはいるが、具体的にその場所を確かめてみようと思っていた。
タンガニーカ湖の南約四百㌔、ルサカ(ザンビア)からタンザニアへ抜けるメーン・ロードから西北へ湿地とジャングルの中を約数十㌔辿ったところにある.四角錐のモニュメントには、リビングストンが忠実で素朴な原住民に看取られながらこの世を去ったことが書かれていた。

広場の中心に一つの井戸があり、円形の草ぶき屋根と、泥の壁という現地人の小さな村、“リビングストン・メモリアル”から、モニュメントまで、草を蹴散らした走る少年に案内して貰わなければ、迷ってしまいそうだった。五十㍍四方くらいの木が切り倒された広場は、草も刈り払われていた。クリクリと目を輝かせた少年は、モニュメントにかじりついたり、囲いのさび付いた鎖に足をかけたりしてはしゃいだ。
 記録によるとこの村は「酋長チタンポの運営」としか書かれていない。元々名前はなかったのだろうが、その子孫達はちゃっかりとイギリス人たちが建てた記念碑を村の名前としてしまっていた。メーンロードには本当に小さな道標が一本立っていた。タテ二十㌢、ヨコ三十㌢くらい。黄色地に黒の字だったが、うっかり見落としそうだった。ひどい道である。長さ一㌔くらいの沼地が三カ所あった。両側は鉄色をした水がアシに似た草の根に絡みついていた。道はと言うと、沼に沈まないように、丸太を置き、盛り土をしてあるだけで、そこが古い車のワダチで、どうにも弱るくらい掘れていた。
記録によるとこの村は「酋長チタンポの運営」としか書かれていない。元々名前はなかったのだろうが、その子孫達はちゃっかりとイギリス人たちが建てた記念碑を村の名前としてしまっていた。メーンロードには本当に小さな道標が一本立っていた。タテ二十㌢、ヨコ三十㌢くらい。黄色地に黒の字だったが、うっかり見落としそうだった。ひどい道である。長さ一㌔くらいの沼地が三カ所あった。両側は鉄色をした水がアシに似た草の根に絡みついていた。道はと言うと、沼に沈まないように、丸太を置き、盛り土をしてあるだけで、そこが古い車のワダチで、どうにも弱るくらい掘れていた。草が深いため、見通しが利かない。落っこちたらズブリと車輪がはまり込んでしまうことは間違いなかった。中山君が降りて先導。
「オーライ、オーライ」である。声を頼りに、窓から首を出しての走行。車の腹をぶつけるたびに、腰を浮かせる有様である。ここを歩いたのではリビングス
 トンでも熱病になるのはムリもなかろうと、余計なことをおもったりする。
トンでも熱病になるのはムリもなかろうと、余計なことをおもったりする。「ずいぶん奥までいったもんだね」
「このヤブと沼、道はなかった時代にな」
このやりとり、如何にも間が抜けていることに気づいた。私はメーンロードからたった50㌔ほどしか“奥地”へ入っていないのだ。リビングストンの時代には、今のメーンロードはなかった。モザンビークか、タンザニアの海岸から徒歩で入った内陸は、道らしきものはなく、動物の踏み跡などの”すべてが道”の世界だった。バングエル湖周辺の湿地帯は確かにひどいけれど、そこへ達するまでの、海岸からの道のりを思うと、あらためてパイオニアたちの体力と精神の強靱さに、畏怖さえ感ずるのだった。
10)支配者達の玄関

奴隷を収容して船を待った施設。今は遊び場になっていた
「バガモヨはどっち?」
「この道をまっすぐ」
「このままでまっすぐか?」
「そうだ。まっすぐ」
タンザニアの首都、ダル・エス・サラームからこんな会話を繰り返しながらクルマを走らせた。バガモヨは百数十年前まで、探検隊や奴隷商人達が,ヨーロッパなどから船でザンジバルへ着き、そこで一休みしてからアフリカ大陸へ第一歩を踏み出したところだ。
探検家・リビングストン(イギリス)、スタンレー(米=英)を始め、多くの探検家や奴隷商人が、ここから奥地へと向かった。だから我々は、今でもバガモヨは賑やかな港町ではないかと考えていた.後輪駆動のマークⅡは、荒れた砂の道で何度も足を取られた。地図と首っ引き。出会う人がいれば、言葉が通じようが通じまいが、お構いなしに訪ねた末に、やっとたどり着いた。

首都ダル・エス・サラームからそう遠くはないのだが、バガモヨの街は、想像していたのとはまるで違う,さびれた街だった。古いアラブ風、ヨーロッパ風の家や、頑丈な要塞が有り、お決まりの教会もあった。様々な国からやってきた“支配者”達の夢のあとでもある崩れた家に、アフリカ人が住んでいた。港はなかった。港の痕跡は石造りの“奴隷囲い”の跡で、ザンジバルを往復する小型船をチェックする役人が三人、その石囲いの中の一室にいた。
年間八万から十万人の奴隷を運び出した港にしては、余りにも静かすぎた。教会へ行ってみた。小さな板にこんな文字が書かれていた。
「奥地で死んだリビングストンが、遙か二千㌔を担がれて海岸にたどり着き、安置されたところである」
リビングストンの遺体を運んだリーダーはスージーとチューマと呼ばれた二人の黒人少年だった.彼らは遺体を切り裂き、内蔵を取り出して腐敗を防ぐため、約二週間の間太陽に晒してから布と樹皮でくるみ、さらにキャンバスを巻いて棒にくくりつけて担いだという。亡くなったところは、リビングストンメモリアルと名付けられて、ジャングルと湿地のなかだった。探検家に忠実な少年は、約九ヶ月かけて、バガモヨまでジャングルと湿地を歩いてたどり着いた。
二人の少年には六十人の人夫達がしたがっていた。アフリカ生まれのアフリカ育ちでも、猛獣のうろつくサバンナやジャングル、湿地帯を歩くのは容易ではない。しかも、よそ者は転々とある部落の、見知らぬ男達に、何時襲われるかも知れない別の危険もあったろう。そしてバガモヨまでの長い距離。リビングストンからバガモヨまで、クルマを走らせて二日間かかった。イギリスの作った道路を、アメリカの援助で拡幅されて、南アからザンビア、そしてタンザニアのダル・エス・サラームまで続いていた。舗装はしてなかったが東アフリカの大動脈だ。
しかし、その道路でさえ曲がりくねった峠道もあったし,緩いうねりを繰り返すサバンナも越えなければならなかった。圧倒的な広さのなかを、幾ら尊敬するリビングストンの遺体とはいえ、棒にくくりつけて交代しながら、九ヶ月も歩き通した精神にはただ感心するばかりだ。教会前の看板は古びて半ば剥げ落ちていた。、書いてあることから、忠実に生きたアフリカ人や少年達の精神を垣間見たように感じた。開発が進み、西欧の影響を強く受けるようになった今日では、こうした純朴で,献身的な心は既に失われてしまったものかも知れない。

遺体を切り開き,内臓を捨てて天日に晒すのは、長い距離を移動するために、長い時間をかけるには合理的な方法だ。誰にも命じられずそれをやってのける知恵にも感動させられる。
「ガイドは要りますか」
なまりのある英語で黒人の青年が近づいてきた。日本円にして三百円ほどで良いという。それではと案内を頼んだ。真っ先に彼は、先ほど見た“港”へ連れて行った。
「ここは奥地から連れてこられた奴隷が集められたところです。五年前まで(1967年)は刑務所だった」
今は税関に変わった“奴隷囲い”を無表情で示した。子供達が檻の跡だろうか、コンクリートの柱が並ぶところで遊んでいた。
11)化粧品はまず脚に

クリンと出っ張った尻に、ごく短い布が巻き付けてある。ミニスカートだけれど、そこから突きだした脚が見事だ。よく「カモシカのような脚」と言うけれど,なぜ,女性の美しい脚をカモシカにたとえなければならないのか、ずっと前から疑問に思っていた。カモシカの脚はぼてぼてと毛が生えていて、短いのに―。
アフリカの女性は、すかっと伸びた脚を誇らしげにさばいて、本当に軽々と歩く。遠くから見ると,ぬめっと黒光りし,は虫類ツヤを連想させる。気味の悪さで言うのではなくするりとした、触ったら滑ってしまいそうな感じを受ける。
その女性はキョロキョロと辺りを見回していた.アフリカの女性が化粧をする場面を,一度でも良いからみたいと考えていたから、チャンス到来である。
場所はナイロビ(ケニア)。ブラックアフリカ随一の近代都市である。東アフリカ鉄道、ナイロビ駅の隅にその女はいた。きっと彼女の視界には、男どもは入っていなかったのだろう。スーツケースを置くと、やにわに化粧品を取り出して脚へ塗り始めた。そうでなくても短い、ミニスカートをまくり上げて擦り込む奮闘である。
鏡を取り出して顔を直すのなら分かるが,脚へアブラを擦り込む有様にはいささかの異様さを感じた。もっともその理由はすぐに判明した。バーで会った男達に尋ねると、あっさりと訳を話した。
「一に脚、二にからだ、三に顔だ」
女性の美しさをはかる目の付け所と言う訳か。これが全て正しいとは言えないけれど,その後、他のアフリカ諸国の男達も「一・脚」のランクは変わらなかったから、基準と言うより,そこに注目と言うところかも知れない。脚の美しさが、何よりも美人?の第一条件となるとしたら,脚に高価な化粧品をたっぷりとしみこませるのは当然と言えよう。事実街では脚専用の高価な化粧品を売っているのだ。

だが、別の理由もある.黒い肌をフト見ると,柔らかくしなやかだと思わざるを得ないが、実は彼女達の五人中、二人までは,少なくとも露出している部分に限って言えば,かなり荒い。“サメ肌”という言葉もあるが,まずそれに近いのかも知れない。生まれてこの方、この部分は乾期のの太陽に照らされ,雨期の湿気にやられ、蠅や蚊を初めとする虫に襲撃されているのだから、やむを得ないのだろう。近づいたり、触ったりしてみなければ、こうした様子はまず分かるまい。
一昨年、イランのカビール砂漠のオアシスで、女が化粧品を欲しがったので,シェービングクリームをやった。それしかなかったのだから,悪気があったわけでは無い。すぐに顔を覆っていた布を外し、顔に塗った。「美の基準は脚」というのは、アフリカのかなり広い地域に共通していたが、中東はそうではなかった。黒い肌は,少しでも脂っ気、水気があると、実に見事な光沢と滑らかさがあるように化けるのだった。
しかし,悲劇的なことに、タンザニア、ウガンダでは今年(注=1972年)女性のミニスカートが禁止された。「なぜ禁止したのか」と尋ねるチャンスはなかったが,ぬめっと光る素晴らしい脚線美が、少なくても東アフリカの二カ国で“見物”出来なくなった。だが、女性はおしゃれの天才なのだろう。カンパラ(ウガンダ)の街角で新しいファッションをみた。超ミニスカートとしか見えなかったが,近くで見ると焦げ茶のぴっちりとした、厚手のタイツをはいていた。ミニンの下にはしっかりとタイツ。これはまた、素肌に勝る遠目の効果はあるようだった。
サバンナで精悍なマサイ族の戦士が、猛獣を相手に槍を振るうー、となれば典型的なアフリカのイメージにつながる.しかし,幾らアフリカと言っても、そうそう旨いシーンを探し出す訳にはいかない。そうした事実が、いまだにあることが分かっていても,実際に目に付くのはマサイ族であることを売り物にした“観光マサイ”だった。

彼らは主として東アフリカのケニア、タンザニア国境付近のマサイ高原に住んでいる。生活の基礎を牛に頼っての放牧生活。
「この世に存在するすべての牛は、神がマサイに与えたもの」という“神話”はいまだに揺らいでいないという。乳と生血を主食とし、外的から自分と牛を守るための槍は、双刃の剣を思わせる凄まじいものだ。
「マサイの写真はマサイの許可なしに撮るな」
多くの観光客がやってくるアンボセリ・ナショナルパークは、マサイランドの中にあるが、ゲートにはこんな文字が書かれていた。外からの文明に背を向け,ひたすら種族の伝統の中に生きる。こんな様子が実感として分かったのは,メーンロードを外れた地域でだった。
 サファリに出掛けたとき「乗せてくれ」という男に会った。
サファリに出掛けたとき「乗せてくれ」という男に会った。「写真を撮らせれば‥」というと、果てしないうねりの続くサバンナをスタスタと歩き始めた。
「水をくれ」と言う男もいた.枯れ草の中で,かなりの数の牛を飼っていたが,’カメラを取り出すと、口もつけずに水の入ったポリタンを投げ捨てて,にらみ据えた。
草原にいる彼らは,赤茶色の汚れたタンガをまとっているだけだが,如何にも誇り高いように見えた。しかし、アルーシャ、モシ(タンザニア)、ナイロビ(ケニア)などの町へ,ビーズ玉細工や木彫りの人形を売りに来る“同族”は、格好こそいくらか綺麗だが,如何にも堕落したように見えるから妙だ。
マサイランドは、キリマンジャロの麓を含め、ケニアとタンザニアにまたがる。彼らはパスポートなしで移動する。イギリス植民地時代に決められた“領土”を守って。タンザニア政府は一九六七年以来「すべての成年男子はズボンをはけ」と行政指導しているが、草原のマサイはタンガ一枚、ズボンをはいている男はいなかった。また、ケニア政府はマサイの牛を食用として活用し、彼らを定着させることに躍起だった。しかし、大多数は、やはりサバンナの中に,草屋根と泥壁の家を作りながら,次々と移動する生活をやめようとはしていない。
13)アフリカの食い物のは意外と旨い。ただし、慎重に見極めて
 太ったオバサンは右手で器用に団子を作った。親指の腹でひょいとくぼみを作り、カレー粉と唐辛子で赤く染まり、べったりと油の浮いたスープにちょっと浸して、旨そうに口へ運んだ。スープの中には鶏のぶつ切りが入っている.今度の旅で最初にであった”ミリミリ”だった。
太ったオバサンは右手で器用に団子を作った。親指の腹でひょいとくぼみを作り、カレー粉と唐辛子で赤く染まり、べったりと油の浮いたスープにちょっと浸して、旨そうに口へ運んだ。スープの中には鶏のぶつ切りが入っている.今度の旅で最初にであった”ミリミリ”だった。「食べてみな。旨いよ」とオバサンは欠けたホーロー容器を二つ、ぐいと私のまえに押し出した。意義手の人差し指、中指を使ってトウモロコシの粉“シマ”を練り上げたものを適当にちぎってスープにつけて食べてみた。唐辛子とカレー粉がぴりりと利き、トウモロコシの粉がざらっとした舌触りで、結構いける。続けてもう一つ、と思ったらおばさんが言った。
「左手でこれを持って,ほら、こうやって食べるんだ」
私にくれたはずの容器の中から、ぶつ切りにされた骨付きの鶏の肉を左手でつかみ出して囓って見せた。ミリミリの中にはごみも砂も混じっているが,そうしたことは腹の減った人間にとって大した問題ではない。トウモロコシの粉を熱湯と油で練る。ちょうど日本の団子を少し緩くした程度の硬さになったところで出来上がり。
呼び名こそ違っても,アフリカ大陸のあちこちで、この種の主食に出会った。タンザニアでは“ウガリ”と呼んでいた。ザンビアではタロイモをまったく同じ方法でこね上げたもの呼び名は“カサバ”だった。
 「日本でもこれに似た団子がある」と言ったら、大喜びしたオバサンは,さらにもう一つのボウルでミリミリを作り、厭と言うほど食わされた。食べ物は決して抱負とは言えないが、日本で考えるような不潔でまずい現地食と言った類いではなかった。ごみが入っているから汚いと決めつけるなら、日本のレストランのキッチンをとっくりと覗いてみるが良い。
「日本でもこれに似た団子がある」と言ったら、大喜びしたオバサンは,さらにもう一つのボウルでミリミリを作り、厭と言うほど食わされた。食べ物は決して抱負とは言えないが、日本で考えるような不潔でまずい現地食と言った類いではなかった。ごみが入っているから汚いと決めつけるなら、日本のレストランのキッチンをとっくりと覗いてみるが良い。神経質な人ならいくら美しく飾り立てた料理でも,ちょっと空気のしなくなるところもある。アフリカの人々は飾ることなく手の内を見せてくれるまでだ。目の前ですべてをやってのける。煮て食べるあおいばななはや果実は実に旨いし“ムシカキ”と呼ばれる焼き肉は、ちょっとした焼き鳥屋や焼き肉屋の味の比ではない。腹が減っているという事を差し引いても,結構な味と言える。
調理は実に単純だ。肉をぶつぎりにして串に刺し、塩と“ピリピリ”(唐辛子)をたっぷりと振りかける。ただそれだけのことだ。私はアフリカの大きな町にいるときでも、バザールや町外れにこの食べ物を探しに行った。ホテルや高級レストランでは味わえないものである。
一昨年、イラクやトルコの田舎町で食べたカバブーも、やはりホテルよりも味が良いように思った。外国人用のホテルや高級レストランでは、凝った味付けをするため、オリジナルの良さが失われているようだった。アフリカではインド料理、、アラブ料理、そしてアフリカ人達の料理が入り交じっていた。牛肉とタマネギを刻み,ピリピリと塩で味付けし、薄皮を巻いて油で揚げた“サモサ”は、ちょうど春巻きのようだった。
もし日本食が恋しくなれば、米を炊けば良い。アフリカの米は日本米ののように、しっぽりと炊きあげることはないが、カナダ米ていどに炊くことは可能だ。コッフェルとコンロを、クルマのトランクから引き出して、何度もも現地で“日本食”を味わった。生水もガブ呑みしなければ何とか喉を潤す程度は問題なかった。ただ、調子に乗って仕舞うとろくなことはないと思う。
後にナイジェリアで酷い目に遭った。
「食え、食え。旨いよ」と盛んに勧められた。何か行事でも会ったのだろう。沢山の露店が出ていて、焼き肉の露店もあった。そこで串焼きの肉を勧められたのだ。口が曲がるほどピリピリを利かせた串焼きだった。食って10分も経ったろうか。全身に痒みが襲った。見ると大きな膨らみ、蕁麻疹だ。初めての事だった。ピリピリでひっくり返るほど辛かったのが、消毒の役でもしたのだろうか。蕁麻疹が治まったら。下痢などの症状も出ずに終わった。やはり食い物は慎重に選ばないといけない。

新聞のl切り抜きから

(読みにくいので、書き直します。手抜きは時間の無駄でした。(;。;))
陰で囁かれる声はアフリカ中の情報を網羅していた。旅から旅を続けるヒッピーたちの髭だらけの口元から、長い髪で隠された耳へ、何となく暗い、そして、してやったりと言った響きと共に…。
ここは東アフリカの中心地。さるホテルの街頭喫茶。通りに面したこの店は、飲み物一杯で何時間でもねばれることが受けて、各国からやってきた若者がたむろする。
「いい情報はないか」
「ないねー」
とさえ言えば彼らと関わりを持つ心配はない。しかし、陸路でヨーロッパへ向かうものに取って、陸路をやってきた連中の情報は貴重だ。そして下手な記録などに比べて、嘘が殆ど混じっていないのもありがたい。コンゴもチャドもスーダンもサハラも、きっと何らかの手がかりがつかめる。しかし、ここで囁かれる彼らの貴重な情報は、税関の状況で有り、ヤミ㌦のようだった。

冬のサハラを越えてきたフランスの青年と親しくなった。二度目に会ったとき「いい情報はないか」とたずねた。「いいよ、教えてやる」と言って連れて行かれたのは郊外のキャンピング場だった。あちこちからオンボロクルマでやってきた連中が、…伝にテントを張ったり、クルマの中に寝たりで生活している。ヒッチハイカーもいる。その青年はいくつかのアフリカの都市の、ヤミ屋の在処を教えてくれた。ついでに符号も。
「オレに合うシャツはないかね」
「ハッ?何でしょう」
「オレに合うシャツをくれ」
ばかげた話しだが、これで暗黙の了解がつく。その店は外人向けのみやげ物屋である。いくらか下着類が置いてある程度だ。
店の主人は経営の実権を握る人物。
「合わせてみましょう。こちらへ」
相手のシャツを品定めが終わるとわざわざシャツを持って店の奥に続くドアをくぐる。さらにもう1つ別の部屋に入ると、ガチンとロックしてやにわに言った。
「「幾ら替える」
「公定レートは1㌦が7シリング(1シリングは43円)だが」
「50㌦なら10シリング、」100㌦なら12それ以上なら13シリング出そう」
情報は正しかった。
別の国でも似たような案配でヤミ屋はあちこちにいた。税関やチェックポイントに対する情報も大変詳しい。隣の国どころか五つや六つも先の“やりにくい国”の様子が手に取るように分かる。
「A国の警官や役人はコインでいい。たばこ一箱ではやり過ぎ」
「b国の税関はタチが悪い。現金を見せると全部換金しろと言うから少しだけ見せろ。滞在日数を考えて、ほどほどにな」
「C国の首都では、サインのないトラベラーチェックでも通用する」
こういう変な情報交換は彼らが旅を続ける方便の一つだろうが、彼らが口にすると不思議い”犯罪”のにおいがしない。何人かに尋ねてみたが、結論はわかりきったものだった。
「倍になるところがあるのに、半額で換える手はないだろう。だいいちここいらの国で換えたカネは他じゃ通用しない。全部その国で使うことになるんだ。幾ら安く買ったって遣っちゃうのだから、この国から儲けるワケじゃない」
外貨を高く買った商人がそれをどうするかは、もうその国の問題だ、とあっさり割り切っているのだった。もっともこうした彼らの動きは、興味こそ有るが、手を染めるわけにはいかない。それよりも何げなく口にする情報の方が、遙かにありがたかった。東アフリカから西アフリカ、そしてサハラ砂漠を越えて北の果てまで、若者たちの誰かが知っていた。
夜、地図を開き、彼らから仕入れた断片的な情報をつなぎ合わせることで、熱帯雨林や砂漠の有様が、次第にはっきりとした形で浮かび上がってくるのだった。

動物公園をクルマで走りました。サイズの関係で切り抜きを2分割しました。ちょっと読みにくいですが…。

1.jpg)