 |
.gif) |
フランス北部への旅

ノルマンディとブルターニュへ
フランスの北部、英仏海峡に面した一帯は、バイキングとして9世紀ごろ北方からやって来たノルマン人が住みついたところ。そのノルマン人にちなんで、この地方はノルマンディとよばれるようになった。またノルマンディの西に続くブルターニュ地方は、5世紀にケルト人がブリタニアから移住して来たことからブルターニュと呼ばれるようになった。後にノルマン人の侵入を受けながら、共にイギリスとの長い攻防の末、15世紀にフランス領となった。
歴史遺産も見逃せないところだが、フランスでも人気の高いカマンベール・チーズの生産地でもある平野が続く酪農地帯と、波の荒い外洋は潮位差の大きいことでも知られ、冷たい海水に育つカキ、エビ、ウニなどの海の幸にも恵まれている。車の旅でなければなかなか行くことができない北部フランスの田舎道を辿りながら、この地方の美しい自然や中世を物語る数多い歴史遺産をたずねてみた。

パリからル・モン・サン・ミッシェルへ
パリ(Paris)-N13(国道)でエヴルー(Evreux)-リジュー(Lisieux)-ドーヴィル(Deauvile)-ル・アーブル(Le Havre)-D513(県道)でカン(Caen)-N175(国道)-ル・モン・サン・ミッシェル(Le Mont St Michel)
1泊2日 距離 約370km
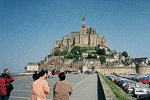
ノルマンディ(Normandie)
●パリ・シャルル・ド・ゴール空港から
エール・フランス機専用の総ガラス張りターミナルF。その広く明るいターミナルを加えて、一層大きく機能的になったフランスの表玄関ド・ゴール空港は、ターミナルごとに大手レンタカー会社のカウンターがあり、どのカウンターからも用意された車の駐車場は近い。
車に荷物を詰め込み、ターミナルをまわり込むように走るとそのままパリ市内に向かって高速道路へ。環状線へ入ると、右左から合流してくる車や分岐点がいくつもあり混乱しそうになるが、行き先の地名とルートナンバーを辿って行けば、それほど難もなく目的地へ向かうことができる。ただ、日本と異なり、3~4車線と車線も交通量も多く、スピードもある。また、当たり前のことだが右側通行だから、最初はくれぐれも注意したい。
●国道N13を走る
 農業国でもあるフランスは、4月から5月にかけて広大な大地が鮮やかな色彩に彩られる。とくに北部では、一面の菜の花と麦の緑が見事だ。芽を吹いたばかりの街路樹の淡い緑の向こうに、黄色と緑の絨毯がどこまでも続く。単調なはずの一本道も、春の色彩は通る人の心を躍らせてくれる。 農業国でもあるフランスは、4月から5月にかけて広大な大地が鮮やかな色彩に彩られる。とくに北部では、一面の菜の花と麦の緑が見事だ。芽を吹いたばかりの街路樹の淡い緑の向こうに、黄色と緑の絨毯がどこまでも続く。単調なはずの一本道も、春の色彩は通る人の心を躍らせてくれる。
街道沿いにはカフェもレストランもないが、街道をはずれた小さな村や町へ寄ってみるのもよい。
フライトが少し遅れたこともあって、ド・ゴール空港を出たのは午後5時を少し回っていた。夏至に近い5月、ヨーロッパは日暮れが遅く、その上サマータイムということもあり、あたりが暗くなるのは午後9時ごろだ。それでも不慣れな道のせいか、空港から100kmくらい走ったところで薄暗くなっていた。折りよく麦畑をはさんで町が見え、そのはずれに一軒のホテルがあった。エヴルー(Evreux)の手前約20kmあたりに位置するパシー(Pacy)という町だ。
最近はヨーロッパもモーテル式の宿が増えたとはいえまだまだ少ないが、ここはそのモーテル式だ。こうした街道沿いの宿は長距離ドライブをする人の利用がほとんどで、目的地に向かってできるだけ走るせいか、夜遅くなって着く人が多い。早めに到着するようにすれば、予約なしでも部屋を確保できる。
●エヴルー(Evreux)のノートルダム大聖堂
 人口5万人ほどのエヴルーの町を迂回すると、N13から大聖堂の尖塔が見える。その塔を目指して町へ向かえば、間もなく大聖堂の正面へ出る。聖堂脇には駐車場がある。 人口5万人ほどのエヴルーの町を迂回すると、N13から大聖堂の尖塔が見える。その塔を目指して町へ向かえば、間もなく大聖堂の正面へ出る。聖堂脇には駐車場がある。
ノートルダム大聖堂といえばパリが有名だが、ノートルダム(Notre-Dame)とは、フランス語で聖母マリアをさし、聖母マリアに捧げた聖堂のこと。12~13世紀にかけてフランス各地に建てられ、ルーアン、シャルトルなど、いずれもフランスゴシックの代表的な聖堂だ。
ちなみにルーアンは、ここより北へ約50km。11世紀に建造された大聖堂は、15世紀の奇跡の少女ジャンヌ・ダルクが処刑されたことでも名高い。また、シャルトルはこれより南約80kmにあり、美しいステンドグラスに魅せられて訪れる観光客で年中賑わう。
有名な二つの大聖堂にはさまれるように立つエヴルーのノートルダム寺院は、12世紀イングランドの王ヘンリー二世が建造を手がけ、後にノルマンディ公においても続行、完成は1260年ころといわれている。その後、いく度か町の火災や外部からの攻撃により破損し修復が繰り返されたが、内部のステンドグラスはガラス芸術の変遷を示すめずらしいものだという。
薄暗い教会内で、突然混成合唱団の美しい讃美歌が流れた。ステンドグラスに見とれている間に、黒一色の服装の合唱団が、マリア像に向かって静かにゆっくり歩きながら美声を奏ではじめたのだ。特別な観光地ではないエヴルーの聖堂は、地元の人々の日常の礼拝場であることを実感させられた。
●リジュー(Lisieux)
 ここからノルマンディの海岸線まで30km足らず。牧草地とリンゴ畑、それに古い藁葺き屋根と石造りの屋敷が点在するのどかな田園風景の中にある町。小さな町だが、ノルマンディ地方の経済の中心地でもある。 ここからノルマンディの海岸線まで30km足らず。牧草地とリンゴ畑、それに古い藁葺き屋根と石造りの屋敷が点在するのどかな田園風景の中にある町。小さな町だが、ノルマンディ地方の経済の中心地でもある。
地元に伝わる聖女の教会カルメル会礼拝堂などがあるが、わざわざ立ち寄ってみるほどのものは少ない。周辺の牧歌的風景を楽しみながら、セーヌ河口にかかる
ノルマンディ橋
へと走る。
河口の西側のオンフール(Honfleur)は、古い漁師町であるとともに石造りの教会や家並みを背景にヨットや小さな漁船の白い帆がゆらぐ光景で多くの画家やカメラマンを魅了する町でもあり、夏は観光客で賑わう。橋の完成前には車で50分もかかったという東側の町ル・アーブル(Le Havre)は工業都市で、港は近代化された港湾施設が並び、第二次大戦後の新市街地だ。
●ノルマンディ海岸

セーヌ河口の町オンフールから西に約100kmほど続く砂浜や岩礁の美しい海岸線で、映画「男と女」のロケ地でも知られている。現在は避暑地、保養地として、春から夏のシーズンには世界各地から多くの観光客を集めている。だが、この海岸線のいくつかのビーチは1944年8月の「連合軍ノルマンディ上陸大作戦」の上陸地だったところ。
褐色の砂、広い砂浜、青い海辺に並ぶ高級住宅街からは戦争の傷痕など伺えないが、ところどころにポツンと記念碑が立つのを見て、当時の激戦の様子を想像してみるのも旅の楽しみの一つだろう。
●ドーヴィル(Deauville)
 ノルマンディ海岸通りの中心部でもあるドーヴィルはパリに代ってフランス社交界の中心といわれるほどの高級リゾート地。夏はアメリカ映画祭、競馬グランプリ(全員正装の特別レース)明け2歳馬国際市、ヨットレースやゴルフ、テニスの試合などが催される。 ノルマンディ海岸通りの中心部でもあるドーヴィルはパリに代ってフランス社交界の中心といわれるほどの高級リゾート地。夏はアメリカ映画祭、競馬グランプリ(全員正装の特別レース)明け2歳馬国際市、ヨットレースやゴルフ、テニスの試合などが催される。
春にはまだその華やかさはないが、高級ホテル、住宅街の庭やテラスに色とりどりの花が咲く風景は夏の華やかさを想像させる。ただ残念なことに、大西洋の水は夏でも冷たく、海水浴には向かない。このドーヴィルからカーブル(Cabourg)までの県道D513号線約10kmは、“花の海岸”といわれている。
○レストラン ラ・ヴェィユ・ショウミェル(La Vieille Chaumiere)
海岸線から少し入った県道(D127)で、白壁に木組と藁葺き屋根の古い民家をそのまま生かしたレストランに出会う。その名も「古い藁葺きの家」。
一目で気に入って中へ入ると、ちようど昼時だったせいか、いくつもないテーブルは地元の人らしい老人たちでいっぱいだった。一つだけ入り口近くに空いていた席に案内されると、日本人の客が珍しかったのか視線を一斉にあびた。

デザートのイチゴは炒めて。なかなかの味だった
フランス語だけのメニューに奮闘しながらも、ノルマンディ名物の生カキを注文。産地だけあってその味はもちろん上等だったが、
デザートのイチゴ
の食べかたが変わっていた。フライパンで炒める。忘れたけれど野菜の葉とワインをかける。生牡蠣を食べたあとだったが、意外と旨かった。
ブルターニュ(Bretagne)
●ル・モン・サン・ミッ
シェル(Le Mont St Michel)
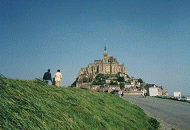 パリから観光客を乗せたバスの多くは、高速道路A13でルーアン(Rouen)を経由して(ルーアンのノートルダム寺院を見学したあと)ル・モン・サン・ミッシェルへやって来る。もう一つ、シャルトル(Chartes)ル・マン(Le
Man)を経由するルートもあるが、どちらも距離的には大差ない。今回はこの2つのルートを結んで一周するかたちになったが、シャルトル方面は別コースとして後で紹介したい。 パリから観光客を乗せたバスの多くは、高速道路A13でルーアン(Rouen)を経由して(ルーアンのノートルダム寺院を見学したあと)ル・モン・サン・ミッシェルへやって来る。もう一つ、シャルトル(Chartes)ル・マン(Le
Man)を経由するルートもあるが、どちらも距離的には大差ない。今回はこの2つのルートを結んで一周するかたちになったが、シャルトル方面は別コースとして後で紹介したい。
ノルマンディの海岸ドライブをしばらく楽しみながら県道(D7)からカン(Caen)を環状線で迂回、国道(N175)を約100kmで一気に西へと走る。高速道路への昇格工事中であり、開通も間近のようだ。黄色い菜の花と緑の麦畑がどこまでも続くのどかな丘陵地帯を流れる車は、数は少ないがどの車も猛スピードで通り抜けていく。
 牧草地から砂地、その 牧草地から砂地、その
向こうに続く広い干潟に忽然と、まるで幻を見ているような石造りの修道院が立っている。
「西欧の驚異」とさえいわれたこの修道院は、8世紀初頭、大天使ミカエル(ミシェル)がモン・トンブ(墓の山)と呼ばれていたこの場所に聖堂を建てたのがはじまりという。もとは陸続きだったが、その昔大津波で森が沈み、岩山だったモン・トンブだけを残して島になったという。
このあたりは潮の干満差が激しく、もっとも大きな潮が押し寄せるのは満月の時と新月の36~48時間後。昔はその差が14mもあったというのだから想像をはるかに超えた自然の驚異だ。
以前は、島は海に浮かび、潮の干満の差を利用して行き来
したが、18mも沖に引いた潮がもの凄いスピードで満ちてくるなかで戻るのに間に合わず、多くの巡礼者が命を落としたともいわれている。島の入り口には今でも潮の干満時刻が表示されているが、現在は島に達するほど潮の干満差はなく、立派な道路と広い駐車場が完備されている。
門をくぐると、さしずめ日本の神社仏閣の参道とい
ったようにレストランやみやげもの屋が狭い石畳の坂道に並ぶ。修道院の全盛期でもあった12世紀のロマネスク様式建築も火災で大部分が失われた。現在は13世紀に再建したゴシック様式のもので、暗い百年戦争にも部分的な破損はあったものの、北部において侵略者イギリス軍の手に落ちなかった唯一の場所である。
階段を上がるごとに眺めはよく、とくに修道院の庭園から望む広い干潟と青い海がよい。ここで受ける風にしばらく浮世を忘れてみるのもいいものだ。
●もう少し足を延ばして
 ル・モン・サン・ミッシェルから海岸づたいに県道(D155)を辿ってみよう。断崖絶壁の崖っぷちをカンカル(Cancale)へ。三陸沖を思わせる海の風景にふと心が和むような気持ちになりながら車を走らせていると、小さな入り江や孤島に城のようなプライベートハウスや小さいながらも重厚なホテルが点在しているのが目に入り、フランスの北海岸の美しさを再確認する。
ル・モン・サン・ミッシェルから海岸づたいに県道(D155)を辿ってみよう。断崖絶壁の崖っぷちをカンカル(Cancale)へ。三陸沖を思わせる海の風景にふと心が和むような気持ちになりながら車を走らせていると、小さな入り江や孤島に城のようなプライベートハウスや小さいながらも重厚なホテルが点在しているのが目に入り、フランスの北海岸の美しさを再確認する。
岩礁に砕ける白波を見ながらしばらく走ると、大きな入り江とその入り江を囲むように立っている頑丈そうな石造りの町が見えてくる。潮の引いた干潟が遠くまで続き、かすかに見える水辺には牡蠣棚がいっぱいだ。
ここはいまでも潮の干満差が激しく、ここからわずか15km西のサン・マロ(St Malo)は、この潮の干満差を利用した世界でも珍しい発電所があるところだ。潮が引くと砂浜の上を、カキを積んだトラックが行き交う豪快な風景となる。
サン・マロ(St Malo)は、16世紀にカナダからの毛皮やタラ漁などで発展した町で、海賊たちの根拠地でもあった。一方、対岸イギリスの侵入に対しては防備のもろさがあり、城壁で囲んだ都市も現在の旧市街は第二次世界対戦後に再建されたもの。いまはこの城壁都市と景勝地としての海岸により観光客を集めている。
○レストラン ル・グラン・ラルジュ(Le Grand Large)

カンカルの町はずれ海岸通りに面したレストラン。日本語に訳せば「大きな海の沖」というように、潮の引いた海はどこまでも干潟がつづいている。この通りには沢山のレストランがあるが、田舎町なのでどこもそれほど変わらない。どの店も売り物は魚貝類、とくに貝類だという。
カキは生で食べるのが普通だが、アサリとムール貝のスープ風のものを注文。ニンニクと香料で味つけしたスープは貝のだしが効いて旨いが、そのはずで、スープといっても貝の量の方が多く、日本流でいえば酒蒸しのようなもの。カキ、あさりとムール貝のスープなどが安くて美味しい。
ノルマンディーは牡蠣の名所。かつてはノルマンディー周辺の海岸には、天然の牡蠣が沢山いて、取り放題だったという。フランス人の牡蠣好きは数百年前から文献に残されていて、ルイ14世は一度に200個、作家のバルザックは144個を食べたなどと言う話しが伝わっている。鉄道が敷かれる前はパリまで馬車輸送だったので、値段は高く裕福な人しか口に出来なかった。

潮の引いた牡蠣の養殖場はトラクターやクルマが走り回って管理・整備をしている。
しかし、味をしめた人々が増えて乱獲。絶滅の危機に気づいた時には手遅れで1840年頃から規制したが絶滅寸前の状態となった。なんとか復活へとこぎ着けたが、1960年には病気が蔓延してほぼ絶滅。ここで宮城県の牡蠣漁業者が種牡蠣をノルマンディーへと空輸。1966年から1980年まで辛抱強く続け、フランスの牡蠣養殖は復活した。。
フランス人の牡蠣好きは生牡蠣の平らな方にまずナイフを入れて上の貝柱を切る。次いで汁を啜り、その後下の貝柱を切って、身をツルリと飲み込む。日本では牡蠣フライなどもあるが、フランスでは生牡蠣一本だ。東日本大震災で宮城県の牡蠣が大打撃を受けた際には”種牡蠣空輸のお返し”で、フランスの牡蠣業者が、養殖場の復興基金や復興資材、義援金などを送ってきている。
ノルマンディーの海岸は、潮の満ち引きが大きいときには10㍍にも達する。牡蠣業者は潮の引いた”海底”に露店を並べ、観光客相手の即売を行っている。また、牡蠣棚の間をトラクターやトラックが走り回り、養殖場の整備などを行っている。日本の牡蠣養殖とは随分と様子が異なる。
|
|
|
|